目次
衆議院と参議院の議席数はどう決まる?日本の選挙制度を徹底解説
日本の二院制とは
日本の国会は、衆議院(下院)と参議院(上院)の二つの議院から構成される二院制を採用しています。この制度は、一つの議院だけでは陥りがちな独断的な決定を防ぎ、より慎重で熟慮された政策決定を可能にすることを目的としています。
衆議院は「世論反映タイプ」として国民の意見をダイレクトに政治に反映させる役割を担い、参議院は「良識の府」「再考の府」として、より長期的な視点から政策を検討する役割を果たしています。
衆議院の議席数の決まり方
衆議院の定数は465人です。議員の任期は原則4年ですが、内閣総理大臣による解散によって任期途中でも全員が一斉に改選される可能性があります。これにより、政治情勢の変化に応じて国民の意思を迅速に反映させることができます。
小選挙区比例代表並立制
衆議院選挙では、小選挙区比例代表並立制という選挙制度が採用されています。この制度では、有権者は2票を投じることができます。
- 小選挙区:289議席
- 比例代表:176議席
- 合計:465議席
小選挙区選挙の仕組み
全国を289の選挙区に分け、各選挙区から1人の議員を選出します。有権者は候補者個人の名前を記入して投票し、最も多く得票した候補者が当選する、シンプルで分かりやすい仕組みです。
この制度のメリットは、地域の代表者が明確になることです。一方で、死票(当選者以外に投じられた票)が多くなりやすいというデメリットもあります。
比例代表選挙の仕組み
全国を11のブロックに分け、政党ごとに候補者名簿を作成します。有権者は支持する政党名を投票用紙に記入し、各政党の得票数に応じて議席が配分されます。
衆議院の比例代表では拘束名簿式が採用されており、政党があらかじめ決めた候補者の当選順位に基づいて当選者が決まります。これにより、政党は戦略的に候補者を配置することができます。
衆議院の優越
憲法により、衆議院には参議院よりも強い権限が認められています。これを「衆議院の優越」と呼びます。
- 内閣不信任決議権:衆議院のみが持つ権限
- 予算の先議権:予算案は必ず衆議院から審議される
- 法律案の再可決権:参議院が否決した法律案でも、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成があれば成立
- 内閣総理大臣の指名:両院の議決が異なる場合は衆議院の議決が優先
参議院の議席数の決まり方
参議院の定数は248人です。衆議院と大きく異なるのは、解散がなく、議員の任期が6年と長いことです。さらに、3年ごとに半数(124人)ずつ改選される仕組みになっています。
この制度により、急激な政治の変化を防ぎ、継続性と安定性を保つことができます。参議院が「良識の府」「再考の府」と呼ばれる理由もここにあります。
参議院の半数改選の仕組み
- 選挙区選出:74議席
- 比例代表選出:50議席
- 合計:124議席
選挙区選挙の仕組み
原則として都道府県を単位として選挙区が設定されています。各選挙区の定数は人口に応じて決められており、有権者は候補者の氏名を記入して投票します。各選挙区で定められた定員分の候補者が、得票数の多い順に当選します。
合区制度について
「一票の格差」を是正するため、2016年の選挙から人口の少ない県を統合する「合区」が導入されました。現在、以下の2つの合区が存在します。
- 鳥取県・島根県選挙区
- 徳島県・高知県選挙区
この制度により、各選挙区の有権者数の格差を縮小し、投票価値の平等性を高めることを目指しています。
比例代表選挙の仕組み
参議院の比例代表選挙は、全国を一つの選挙区として行われます。衆議院とは異なり、非拘束名簿式が採用されているのが大きな特徴です。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 比例代表の方式 | 拘束名簿式 | 非拘束名簿式 |
| 投票方法 | 政党名のみ | 政党名または候補者名 |
| 当選者の決定 | 政党の順位による | 個人の得票数による |
参議院比例代表の投票方法
参議院の比例代表では、有権者は支持する政党名または候補者の個人名のいずれかを記入できます。各政党の議席数は、政党名と候補者名の票の合計である総得票数に応じて、ドント方式で配分されます。
ドント方式とは、各政党の得票数を1、2、3…の整数で順に割り、その商が大きい順に議席を配分する方法です。この方式により、得票数に応じた比例的な議席配分が実現されます。
ドント方式の計算例(5議席を配分する場合)
特定枠制度
2019年の選挙から導入された「特定枠」は、政党があらかじめ指定した候補者を、個人の得票数に関わらず優先的に当選させる仕組みです。特定枠の候補者は、以下のような制限があります。
- 選挙事務所の設置不可
- 選挙カーの使用不可
- ビラやポスターの掲示不可
- 個人演説会の開催不可
この制度は、全国的な支持基盤は持たないが国政上有用な人材や、合区により選挙区で立候補できなくなった現職議員の救済策として導入されました。
投票権と被選挙権
日本の選挙における投票権(選挙権)と被選挙権(立候補できる権利)には、以下のような年齢制限があります。
| 投票権 | 被選挙権 | |
|---|---|---|
| 衆議院 | 満18歳以上 | 満25歳以上 |
| 参議院 | 満18歳以上 | 満30歳以上 |
2016年の公職選挙法改正により、投票権の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、より多くの若者の声を政治に反映させることが期待されています。
選挙の実施時期
衆議院選挙は、任期満了(4年)または解散により実施されます。実際には、戦後のほとんどの衆議院選挙は解散によるものです。
参議院選挙は、3年ごとに定期的に実施されます。2025年の参議院選挙は、任期満了が7月28日であることから、一般的に7月3日公示、7月20日投開票になると予想されています。選挙運動期間は公示日から投票日の前日までで、少なくとも17日間となります。
まとめ:二院制が実現する民主主義
日本の衆議院と参議院は、それぞれ異なる選挙制度と役割を持つことで、多角的な視点から国政を運営する体制を築いています。衆議院は国民の最新の意思を反映し、参議院は長期的視点から慎重に審議することで、バランスの取れた政治運営を可能にしています。
選挙制度は複雑に見えるかもしれませんが、それぞれの仕組みには明確な目的があります。小選挙区制は地域の代表を、比例代表制は多様な民意を、そして二院制は慎重で安定した政治を実現するために設計されています。
有権者として重要なのは、これらの制度を理解し、自分の一票がどのように議席に反映されるかを知ることです。18歳以上の全ての国民が持つ投票権は、民主主義の基盤となる大切な権利です。次の選挙では、ぜひこの知識を活かして投票に参加してみてください。
参考リンク:

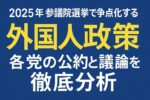

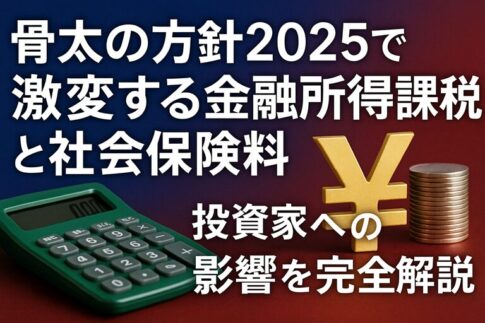
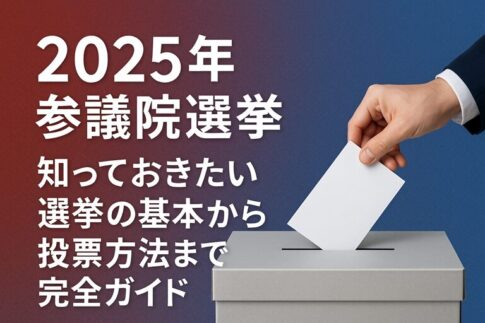

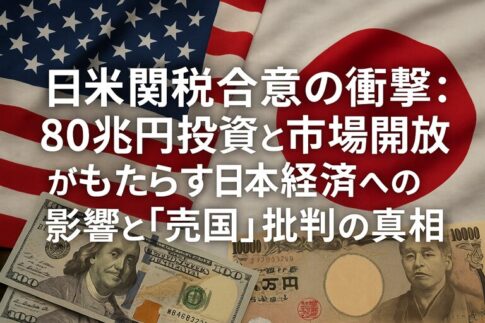
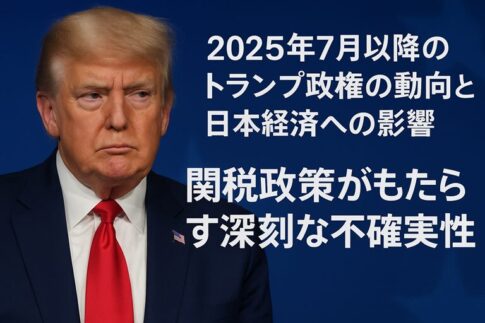

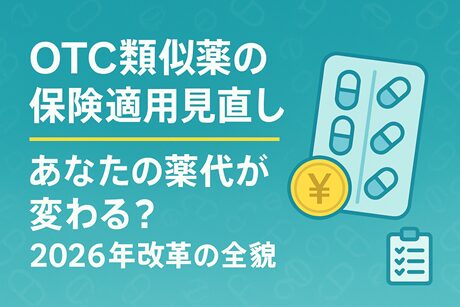



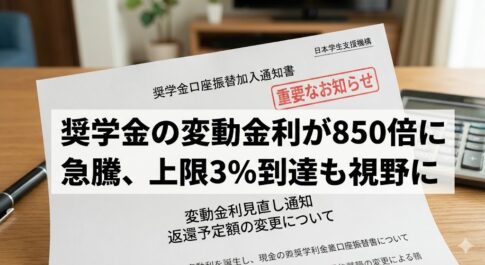
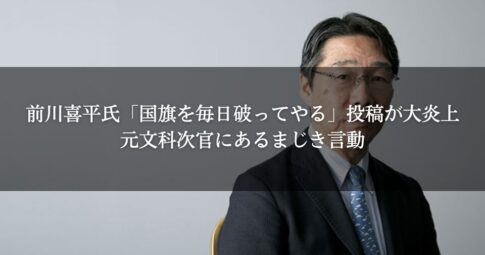





コメントを残す