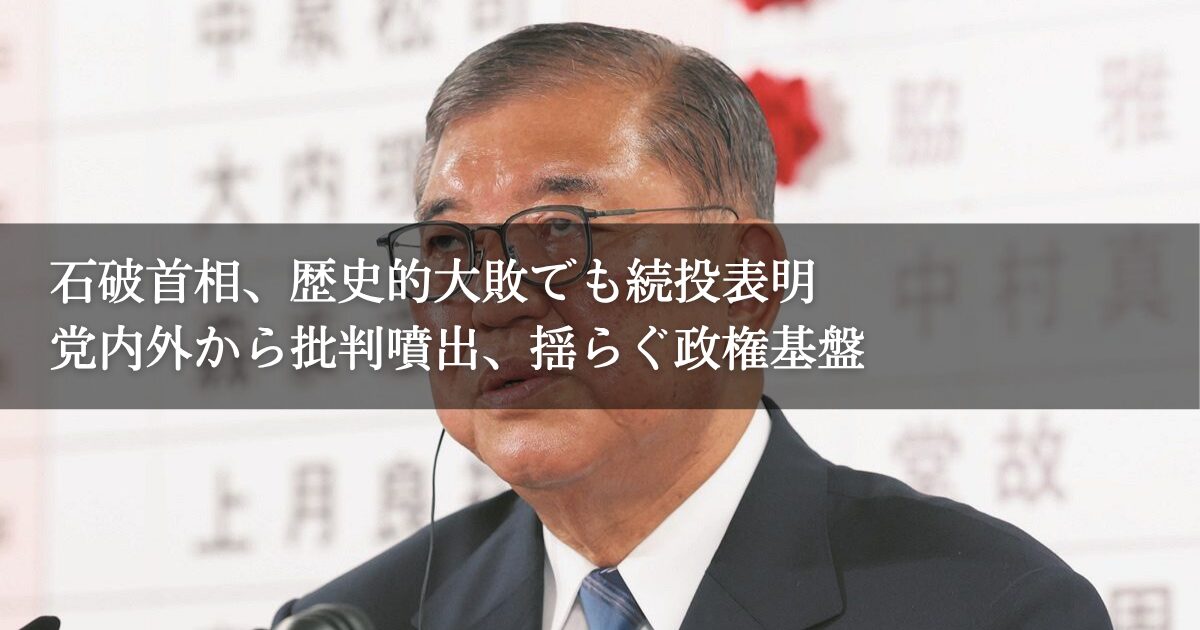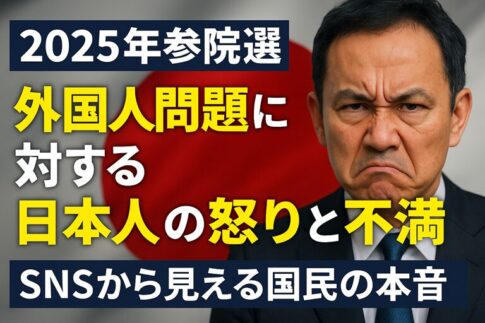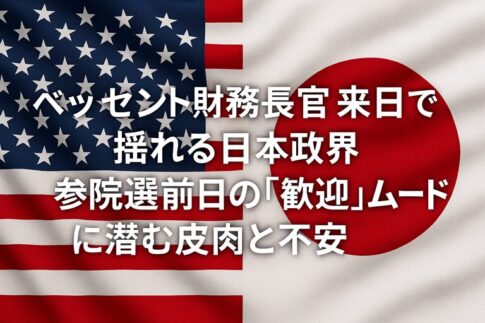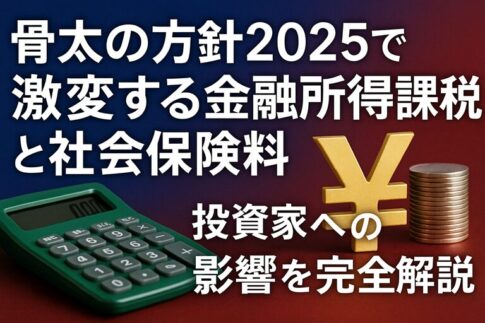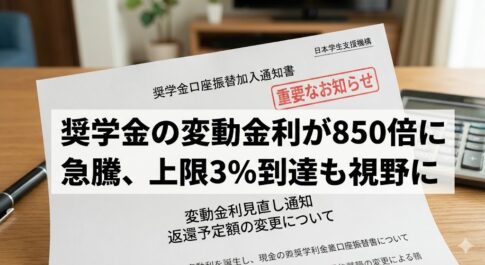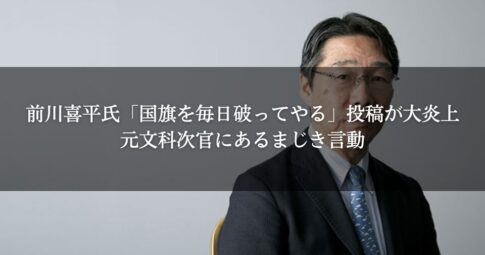目次
- 1 石破首相、歴史的大敗でも続投表明 – 党内外から批判噴出、揺らぐ政権基盤【徹底検証】
- 1.1 石破政権の船出 – 「友達作りの下手な石破茂」の苦難
- 1.2 衆議院選挙(2024年10月)- 自民党結党以来初の過半数割れ
- 1.3 東京都議会議員選挙(2025年6月)- 過去最低議席という屈辱
- 1.4 参議院選挙(2025年7月)- 歴史的惨敗と「少数与党」への転落
- 1.5 石破首相の続投表明と正当化の理由
- 1.6 「重く受け止める」発言への痛烈な批判
- 1.7 「首都直下型地震で辞めない」発言の大炎上
- 1.8 給付金政策を巡る公約撤回疑惑
- 1.9 党内から噴出する「石破おろし」の動き
- 1.10 「政治とカネ」問題への不誠実な対応
- 1.11 野党の反応と新興勢力の台頭
- 1.12 今後の政権運営と山積する課題
- 1.13 国民が抱く不満の数々 – 政策批判の声
- 1.14 石破首相への個人批判 – 資質と言動への疑問
- 1.15 結論 – 日本政治の重大な岐路
石破首相、歴史的大敗でも続投表明 – 党内外から批判噴出、揺らぐ政権基盤【徹底検証】
2025年7月20日に投開票された参議院選挙で、自民党は改選52議席から39議席へと大幅に議席を減らし、歴史的な大敗を喫しました。石破茂首相は「痛恨の極み」「重く受け止める」としながらも続投を表明。しかし、この決定に対し、党内外から前例のない規模の批判が噴出しています。本稿では、石破政権の誕生から参議院選挙での惨敗に至るまでの全過程を、国民の声や党内の動向を交えながら徹底検証します。
石破政権の船出 – 「友達作りの下手な石破茂」の苦難
石破茂氏は、5度目の挑戦でようやく自民党総裁の座を射止めました。しかし、その選出過程から既に暗雲が立ち込めていました。テレビコメンテーターからは「友達作りの下手な石破茂」と揶揄され、人付き合いに対する評価の低さが露呈していました。
さらに、かつて自民党を離党し、政権交代を唱えて小沢一郎氏らのもとに馳せ参じた経歴は、自民党一筋の国会議員たちの間に複雑な感情を残していました。2012年の総裁選で党員票に支えられてトップに立ったものの、決選投票で安倍晋三氏に逆転された経験は、その複雑な感情が影を落としていたことを如実に示しています。
歴代最低の内閣支持率でスタート
・発足時:約30%台(危険水域)
・2025年3月:27.9%(現行調査方式での歴代最低)
・不支持率:30.1% → 44.1%へ上昇
これは、岸田内閣(発足時59%)や菅内閣(同68%)を大きく下回る数字でした。支持しない理由として最も多かったのは「政策が駄目」(12.7%→17.2%へ増加)、次いで「リーダーシップがない」(12.6%→14.5%へ増加)でした。
「石破カラー」の不在が支持率低迷の要因
長年「党内野党」として歯に衣着せぬ発言を続けてきた石破氏ですが、首相就任後は日米地位協定改定などの持論を封印。従来の批判的視点が政権運営において建設的な政策実現能力へと転換できていないという見方が支配的となりました。
さらに致命的だったのは「政治とカネ」の問題でした。石破首相が自民党議員との会食の際に1人当たり10万円分の商品券を配っていたことが発覚。世論調査では実に71.6%が「問題だ」と回答し、長年「清廉な金銭感覚」と「政治改革」を訴えてきた石破氏の政治的理想と現実の政治運営の間に深刻なギャップがあることが露呈しました。
衆議院選挙(2024年10月)- 自民党結党以来初の過半数割れ
選挙の背景と争点
石破内閣は発足直後の2024年10月9日に衆議院を解散し、10月27日に投開票が行われました。この選挙の最大の争点は、自民党派閥による裏金問題でした。
石破首相は「政治は国民のもの」という原点に立ち返って政治改革と党改革に取り組むと表明。特に、旧文通費(調査研究広報滞在費)の使途公開と残金返還、そして政策活動費の廃止を含む白紙的な議論を行うと決断したと述べました。
しかし、国会答弁では自民党候補のいない支部に2千万円を支給していた問題に対し、「支部が存在しない場合には、当然ながら支給していない」とごまかし、その後も答弁が二転三転。最終的には「倫理的な後ろめたさはない」と開き直るなど、無反省な姿勢を見せたとの批判を浴びました。
衆議院選挙の結果 – 歴史的敗北
2024年衆議院選挙結果
| 政党 | 選挙前議席 | 獲得議席 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 自民党 | 276 | 191 | -85 |
| 公明党 | 32 | 24 | -8 |
| 与党合計 | 308 | 215 | -93 |
| 立憲民主党 | 96 | 148 | +52 |
| 国民民主党 | 7 | 28 | +21 |
| 日本維新の会 | 44 | 44 | ±0 |
投票率:約56.3%(前回55.93%から若干上昇)
与党は過半数(233議席)に18議席届かず、1955年の自民党結党以来初めて衆議院で与党が過半数を失う事態となりました。
この結果を受け、法務大臣の牧原秀樹氏と農林水産大臣の小里泰弘氏が落選。それぞれ鈴木馨祐氏と江藤拓氏が後任に起用されました。公明党代表の石井啓一氏も落選し、新代表となった斉藤鉄夫氏に代わり、中野洋昌氏が国土交通大臣に就任しました。
自民党内部の反応
衆議院選挙で過半数を割った際、自民党内では石破首相への退陣を求める動きは限定的でした。これは、当時の争点が安倍派の裏金問題であり、石破首相個人の責任が直接的に問われにくい状況だったためです。
しかし、党内には今回の対応(政治資金問題に関与した議員の党公認を巡る混乱や、非公認候補の党支部への2000万円支給)をとった石破首相や森山裕幹事長ら党執行部への不満がくすぶっていました。特に、森山裕幹事長が選挙での公認権を悪用し、中間派を締め付けていたという指摘も出ていました。
東京都議会議員選挙(2025年6月)- 過去最低議席という屈辱
選挙前の政策転換と期待
2025年夏の参議院選挙を控え、その前哨戦として位置づけられた東京都議会議員選挙を前に、石破政権は支持率回復と物価高対策を喫緊の課題と捉え、いくつかの政策転換を図りました。
「コメは買ったことがない」発言で批判を浴びた江藤拓農水相を更迭。後任に小泉進次郎氏を起用し、随意契約による政府備蓄米の売り渡しを開始。5キロ2000円台の備蓄米がスーパーに登場。
国民1人当たり2万円、子どもには追加2万円の現金給付を公約に盛り込むことを決定。当初消費税減税を否定していたが、「無策では参院選を戦えない」という与党内の声に押された形。
森山裕幹事長をはじめとする自民党執行部は、「コメの大消費地である東京で、コメの価格引き下げは有権者に強くアピールするはず」と期待を寄せていました。この備蓄米放出後、内閣支持率や自民党の政党支持率は若干上向いたとされています。
都議選結果と国民の反応
2025年東京都議会議員選挙結果
自民党:前回30議席 → 過去最低の21議席
第一党の座を失う
この結果は、昨秋の衆議院選挙で自民・公明の与党が過半数を大幅に割り込んだ現実が「根が深い」ことを改めて示すものとなりました。小泉農水相の起用による「進次郎効果」も、都議選で目立った効果が出るまでには至りませんでした。
給付金政策への国民の反応
石破首相が選挙直前に現金給付を打ち出したことに対し、国民からは厳しい批判が相次ぎました。
「選挙前のバラマキだよね」
「ただの票集め」
「やるなら減税でしょう」
「国民から取った金を配るのが公約って凄すぎ」
「ばらまく前に余分な税金を取らないようにしてください」
「給付金で喜んでいる人もいますが、税金めちゃめちゃ取られているのにと思います。カツアゲされた奴からご飯おごってもらって喜んでいるのと同じです」
さらに、過去の石破首相の発言が掘り返され、公約への不信感を増幅させました。
(2024年12月、国会予算委員会での石破首相発言)
「選挙が終わったら撤回もあり得る」
「国民を馬鹿にしてる感じがほんと腹立つ」
参議院選挙(2025年7月)- 歴史的惨敗と「少数与党」への転落
選挙前の状況と勝敗ライン
石破首相は、今回の参議院選挙の勝敗ラインを「非改選議席を含め、自公で過半数(50議席獲得)」と明確に公言していました。これは、故・安倍晋三元首相や岸田文雄前首相なども国政選挙前に示していた「大甘の勝敗ライン」であり、通常であれば容易にクリアできる目標とされていました。
・時事通信:支持率20.8%(発足後最低)、不支持率55.0%
・毎日新聞:支持率23%、自民党支持率19%
・「青木率」(内閣支持率+与党支持率):42%(危険水域)
選挙戦の最大の争点として浮上したのは物価高対策でした。出口調査によると、約48%の有権者が物価高対策を投票で最も重視したと回答しています。また、米国との関税交渉、特に8月1日に迫る関税措置の発動は、選挙後の政局にも大きな影響を与える国家的重要課題として認識されていました。
参議院選挙結果 – 衆参両院で少数与党という異常事態
2025年参議院選挙結果
| 政党 | 改選議席 | 獲得議席 | 非改選含む総議席 |
|---|---|---|---|
| 自民党 | 52 | 39 | 83 |
| 公明党 | 11 | 8 | 39 |
| 与党合計 | 63 | 47 | 122 |
| 立憲民主党 | 22 | 22 | 44 |
| 国民民主党 | 4 | 17 | 21 |
| 参政党 | 0 | 14 | 14 |
| 日本維新の会 | 13 | 7 | 20 |
投票率:58.51%(前回52.05%から6ポイント以上上昇)
期日前投票者数:2618万1865人(有権者全体の25.12%、過去最多)
・与党は目標の過半数(125議席)に3議席届かず122議席
・衆参両院で与党が過半数を割る「少数与党」は1955年の自民党結党以来初
・参議院で少数与党は野田内閣以来14年ぶり
・衆参両院で少数与党は羽田内閣以来31年ぶり
注目の落選者
自民党の比例代表では、保守系候補の落選が相次ぎました:
- 佐藤正久幹事長代理(「ヒゲの隊長」)
- 山東昭子元参院議長
- 赤池誠章氏(保守団結の会)
- 杉田水脈元衆院議員
- 和田政宗参院内閣委員長
- 長尾敬元衆院議員
石破首相の続投表明と正当化の理由
石破首相は参議院選挙での大敗を受けても、即座に続投する意向を表明しました。その理由として以下を挙げています:
1. 国家・国民への責任の強調
2. 国政の停滞回避
石破首相は、以下の「国難」を理由に政治の空白を避けるべきだと主張:
- 8月1日に迫る米国との関税措置への対応
- 物価高対策
- 自然災害への対応
- 戦後最も複雑で厳しい安全保障環境
3. 期限の不設定
続投の具体的な期限は設けていないと明言し、事実上の無期限続投を示唆しました。
「重く受け止める」発言への痛烈な批判
石破首相が敗北を「重く受け止める」と繰り返したことに対し、ジャーナリストの江川紹子氏などから批判が噴出しました。
さらに、過去の発言との矛盾も指摘されました。かつて麻生太郎首相(当時)に対し「私なら辞める」と公然と批判した石破氏の言葉が、今回「自らに跳ね返っている」状況だと報じられています。
「首都直下型地震で辞めない」発言の大炎上
石破首相が記者会見で述べた「首都直下型地震で辞めない」という発言は、SNS上で大炎上しました。
「石破自身が国難」
「首相が未来を知っていて、災害から日本を救うために何度も人生をやり直している『タイムリープ説』まで登場」
「こんなに長く総理でいたいのか?」
「今の自民党が政権を握っている事が国政の停滞なのでは?」
この発言は、単なる首相個人への批判に留まらず、根深い政治不信と来る災害への国民の本気の不安が入り混じった、国民の本音の表れであると分析されています。
給付金政策を巡る公約撤回疑惑
参院選後、石破首相の給付金政策に対する姿勢が大きな批判を浴びました。
給付金政策の内容
・全国民一律:2万円
・住民税非課税世帯:追加2万円(合計4万円)
・子ども1人につき:2万円加算
・7月10日のテレビ番組では「現金給付は1回に限らず」と発言
・財源:税収の上振れ分(約1兆5000億円〜2兆円)と税外収入(約1兆円)
「給付中止」騒動と過去発言の発掘
石破首相が敗因分析として述べた「非常に困っている家庭に、早く手厚い対策を打っていくということがなかなか理解を得られなかった」という発言が、共同通信の報道で「給付中止」と誤解され拡散しました。
石破首相は「選挙結果の分析であり、給付中止の発表ではない」と釈明しましたが、より決定的だったのは過去の発言の発掘でした。
(2024年12月、国会予算委員会での石破首相発言)
「選挙詐欺だった」
「公約など一切守る気のない石破首相😫‼️」
「幼児でもルール守れます」
「公約も守らないのが自民党って言ってたもんな〜石破くん」
「現金給付するかも(本当はしない)と言っておけば票を入れると思われてる、国民を馬鹿にしてる感じがほんと腹立つ」
党内から噴出する「石破おろし」の動き
地方組織からの異例の退陣要求
自民党高知県連は緊急役員会を開き、参院選敗北の責任を取り、「国民の民意に沿って石破総裁が早期に退陣すべきである」として、党本部に申し入れる方針を決定しました。地方組織からの異例の行動であり、この動きが全国の都道府県連に広がることを期待する声も聞かれます。
有力議員からの痛烈な批判
主な退陣要求・批判発言
- 西田昌司参院議員(京都選挙区で当選)
「国民から見放された人が次々モノを言っても信頼性がないわけですよ」
「僕はもう一度、筋から考えて総理は責任をとられるべきだし、新しい総裁を選ばなければならない」 - 麻生太郎・自民党最高顧問
麻生派を緊急に集め、「続投は認めない」と周囲に語ったと報道。事実上の退陣勧告。 - 小林鷹之元経済安保相
「国民から自民党に対して最後通牒を突きつけられた」
「責任は非常に重い。総理総裁が判断することと思うが、責任の重さを党のトップとしてしっかり受け止めていただきたい」 - 落選議員たち
「まずは総理が辞任するところから始めなければならない」
党内では、「昨秋の衆院選、6月の東京都議選に続く重要選挙3連敗で『スリーアウト・チェンジ』」との声が噴出。選挙終盤には「多くの接戦区の自民党陣営が、『票が減る』と石破首相の応援を断るケースが相次いだ」とも報じられ、「石破首相の不人気が自公の過半数割れの最大の要因」という厳しい声が支配的でした。
「石破おろし」が本格化しない背景
強い退陣要求が噴出しているにもかかわらず、「石破おろし」が本格化する兆しは必ずしも明確ではありません。その背景には以下の要因があります:
1. 党内のエネルギー不足
「少数与党になり、もう党内にそんなエネルギーはない」(閣僚経験者)
2. 責任の転嫁と求心力の限界
衆院選での過半数割れ時には、安倍派の裏金問題が争点だったため、石破首相個人への退陣要求は限定的でした。今回は石破首相自身が勝敗ラインを明言していたにもかかわらず、「石破自民は史上最弱の自民党だ。なのに自民党はこの程度の負けで済んだ」という見方も一部に存在します。
3. 政治空白への懸念
首相が辞任すれば、党内の激しい権力闘争が始まり、政治が停滞することを懸念する声も続投を後押ししています。
4. 森山幹事長の関与と保守派の不満
昨年秋の居座りについては、森山裕幹事長が選挙での公認権を悪用して中間派を締め付けていたこと、さらに自民党内の保守系のベテランが党員資格停止や除名されたままであったため、5月まで身動きが取れないようにされていたという事情が指摘されています。
しかし、参院選が終わった今、森山幹事長が公認権を振り回しても通用せず、自民党内の保守派や地方組織は党をここまでボロボロにしたことに納得しておらず、「これ以上我慢ならん」というところにきているという指摘もあります。
5. 「ポスト石破」を巡る動き
退陣となれば、「ポスト石破」として高市早苗氏(元経済安保相)、林芳正氏(官房長官)、小泉進次郎氏(農水相)らの名前が挙がっています。特に高市氏には「待望論」がある一方で、その求心力が目立った伸びに繋がっていないことも、石破氏の続投を助長している可能性が指摘されています。
「政治とカネ」問題への不誠実な対応
石破首相の「政治とカネ」問題への対応も、国民の不信感を増幅させました。
国会答弁での迷走
自民党候補のいない支部への2000万円支給問題について:
- 当初:「支部が存在しない場合には、当然ながら支給していない」と曖昧な答弁
- 追及後:「自民党候補がいない支部に『自民党が出ておる支部と同等の対応をしているということは、むしろおかしい』」と2千万円不支給を認め開き直り
- 裏金非公認候補への支給について:「当然、事情は異なる」とはぐらかし
- 最終的に:「倫理的な後ろめたさはない」と無反省ぶりを示す
政治資金改革への姿勢
石破首相は政治資金の透明性確保のために「ガラス張りにする」として、収支報告のDX化を推進すると表明。政策活動費についても廃止を含めた白紙的な議論を決断したと述べました。
しかし、企業・団体献金については:
「(30年前の政治改革で企業・団体献金廃止の方向となったことについて)そういう事実は実際にございません」
これは、国民の政治資金問題に対する根強い不満と乖離した認識であると批判されました。
野党の反応と新興勢力の台頭
既存野党の批判
立憲民主党・野田代表:
国民民主党・玉木代表:
新興政党の躍進
参政党は「日本人ファースト」を掲げて選挙区7、比例7の計14議席を獲得する大躍進を遂げました。これにより、参政党は単独で法案を提出することが可能になりました。
党首の神谷宗幣氏は、グローバリズムへの対抗や日本国民の生活再建を意味すると説明していますが、「移民への強硬姿勢」が主張の核心にあると指摘されています。彼の主張は、経済の停滞と社会の変容に対する有権者の深い不安を突く内容となっています。
「参政を通さないために今回だけは公明に入れる」(リベラル層の声)
今後の政権運営と山積する課題
少数与党下での国会運営
予算編成の難航
2025年1月召集の通常国会では、2025年度予算案の成立が最優先課題となりますが、衆議院が少数与党に転落したため、野党の合意なしには予算案が通らなくなりました。予算案が遅れた場合、新年度の4月から予算を執行できず、国や自治体の事業に影響が出る可能性があります。
野党との協調と妥協
石破首相は「できるだけ多くの党の理解を得て、丁寧に、そして、謙虚に国民の皆様方の安心と安全を守るべく取り組んでまいる」と述べていますが、野党第一党の立憲民主党や国民民主党、日本維新の会は、現時点では連立拡大に否定的です。
財政ポピュリズムへの懸念
参議院選挙前から、与党以外の多くの政党が消費税減税や現金給付に積極的な姿勢を見せており、自公過半数割れに至った場合、程度の差こそあれ「拡張財政路線の強まりが不可避」という情勢になると指摘されています。
日米関係と国際的影響
トランプ関税問題
・2025年4月:日本を含む複数国に対し24%の「互恵関税」を発表
・自動車や鉄鋼、アルミニウムに25%の関税
・7月9日:一時停止
・8月1日:再発動の警告
・日本の首席交渉官:赤澤亮正経済再生担当相(交渉は難航)
日本の輸出経済は米国(輸出の21%)と中国(19%)に大きく依存しており、トランプ政権が中国への関税を145%に引き上げる中で、日本は米中間の板挟みに直面しています。
- トヨタ:関税による利益減を1300億円と予測
- ホンダ・日産:業績悪化を懸念
- 米メディア:「少数与党化で日本の交渉力低下が顕著」と報道
「経済悪化が避けられない」
「少数与党で交渉力が弱い日本が不利」
「経済がさらに悪化する」
「日本は実質的にアメリカの植民地」論
トランプ大統領の強硬姿勢は、同盟国の自立を促す一方で、伝統的な西側の結束を揺るがしています。このような状況で、「日本は実質的にアメリカの植民地だ」と国民が気づき始めたという見方も存在し、財務省解体デモや日米地位協定の見直しを求める声も上がっています。
国民が抱く不満の数々 – 政策批判の声
参議院選挙を通じて、国民からは様々な政策への不満の声が噴出しました。
海外援助への批判
「9人に2.4億?1人2,700万円。そんなにかける価値があるのか」
「その前に日本の奨学金返済地獄どうにかしてくれ」
「”無償協力”って結局、俺たちの税金じゃないのか?」
「ブータンとの友好も大事だけど、国民生活はもっと大事だろう」
「留学生よりも、日本の若者に給付型の奨学金を出すべきだ」
「60万ドルあったら国内の小中学校のパソコン環境整えられるだろ」
「また海外にばら撒き。減税とか国内支援はいつやるの?」
「モルドバの司法改革より、日本の司法改革の方が必要じゃない?」
「これって誰が喜ぶの?結局は外務省の実績作りでしょ」
「援助したって、日本企業の進出先になるわけでもない」
行政のIT化の遅れ
「まず日本の病院や役所のITセキュリティ強化しろよ」
「地方に行ったら未だにWindows7とか普通にある」
「自治体の職員が標的型メールに引っかかるの、何回目?」
「行政のIT化が遅れてるのは国の責任じゃないの?」
観光公害への不満
「観光客のマナーが悪く、住民の生活がストレスに」
「観光業者は儲かっても、地元住民は困ってるだけ」
「トイレもゴミ箱も足りず、放置されたまま」
「利益が地域に還元されていない。迷惑料すら欲しい」
「観光っていうより”観光地だけの経済”」
「生活の場を”見世物”にされてる感じがする」
「年間数百万人が来ても、地元には税金も還元もなし」
「対策がなければ、もう観光客いらないって声も出てきそう」
「”おもてなし”の前に、”地域との共生”を考えて」
最低賃金引き上げへの懸念
「人を雇えば赤字。設備投資やIT化の余裕なんてない」
「地方ほど最低賃金の負担は重くなる」
「賃上げが実現すれば、地域経済全体の底上げになる」
「良い人材が地方でも採用できるようになる」
「やるなら政府が徹底的に支援してくれ」
外国人免許切り替え制度への批判
「あの事故は本当に許せなかった。ようやく対策か」
「日本人が同じことしたらもっと厳しいはず」
「観光客向けに免許発行してたのが異常」
「遅すぎるけど、やらないよりマシ」
石破首相への個人批判 – 資質と言動への疑問
石破首相の言動や資質に対しても、国民から厳しい批判が相次いでいます。
選挙応援での「助けてください」発言
参院選の応援演説で石破首相が述べた「助けてください。山下のためではありません、日本のために」という感情に訴える発言は、SNS上で冷ややかな反応を招きました。
「助けたくありません」
「情けない、一国の総理ともあろう者が」
「助けてほしいのは国民のほう」
これは、議席死守に意識が向きすぎて、本来あるべき応援から逸脱した印象を与えてしまったと分析されています。
民主主義への姿勢を問う声
「国民は首相公選か大統領制を要求することになる」
「『自分がやることが最善』『責任=辞職ではない』という傲慢な考え」
「けじめ」として辞任することが当たり前
「そのズレが、不信感や政治不信に更につながっていく」
続投への執着を疑問視する声
「自民は岸破を処理できなければ終わると思いますね。」
「有権者もそれを願って自民には入れなかったのだろうと思います。」
「浅はかだけどね…」
結論 – 日本政治の重大な岐路
石破茂首相は、衆議院選挙、東京都議会議員選挙、そして参議院選挙という重要選挙で3連敗を喫しながらも、続投を表明しました。しかし、この決定は以下の点で深刻な問題を抱えています:
- 民主主義の原則との乖離:国民の審判を3度も受けながら続投することへの正当性への疑問
- 党内からの信頼喪失:地方組織を含む党内各層からの退陣要求
- 公約への不信感:給付金政策を巡る撤回疑惑
- 国際交渉力の低下:少数与党化による対外交渉への影響
- 政治の停滞:野党との協調が不可欠な中での政策実現の困難
石破政権の真の価値は、政権の存続期間よりも、日本政治に与える質的変化にあると考えられます。彼の「協調型政治運営の実験」、データ重視の政策評価、説明責任を重視する政治文化の醸成といった取り組みが、将来の政治運営のモデルとなる可能性があります。
しかし、現実には国民の政治不信が根深く、経済への不安が広がる中で、石破政権がどのように求心力を維持し、山積する課題に対応していくのか。「石破おろし」が本格化するのか、それとも少数与党のまま政権運営を続けるのか。日本の政治は、まさに重大な岐路に立たされています。
この不安定な状況が、日本の政治文化に新たな変革をもたらす契機となるのか、それとも更なる混迷を深めるのか。その答えは、今後の石破首相の政治判断と、国民・党内の反応にかかっているでしょう。