目次
2025年7月以降のトランプ政権の動向と日本経済への影響 – 関税政策がもたらす深刻な不確実性
2025年7月に入り、ドナルド・トランプ米大統領の政策が世界経済と日本に前例のない影響を与えています。特に注目されるのが、日本を含む広範な国々への追加関税措置と、それが引き起こす経済的・政治的な波紋です。本記事では、調査資料に基づき、7月以降のトランプ大統領の詳細な言動と、それが日本経済、政治、そして国民生活に与える多面的な影響について包括的に分析します。
2025年7月以降のトランプ大統領の主要な言動
7月1日:イスラエル・ガザ停戦合意への言及
トランプ大統領は、イスラエルがガザ地区での60日間の停戦合意に必要な条件に合意したとSNSに投稿しました。中東の停戦合意を発表することで、金融市場にも影響を与えています。しかし、停戦が短期で終わる可能性も懸念されており、地政学リスクは依然として価格上昇要因となり得ます。
7月2日:米国内政策と貿易協定の大規模発表
この日、トランプ大統領は矢継ぎ早に複数の重要政策を発表しました:
- ロサンゼルス市を提訴:「聖域都市」政策を巡って法的措置を取りました
- AI人材育成の推進:60社以上が参画する取り組みを発表
- キューバに対する規制強化:対キューバ強硬姿勢を鮮明に
- ベトナムとの貿易協定合意:米中摩擦の中で重要な動き
- シリア制裁解除:大統領令により制裁を解除
特にベトナムとの貿易協定は注目に値します。ベトナムは米中摩擦の激化で「漁夫の利」を最も得た国の一つですが、トランプ氏は第三国からベトナムを経由した輸入品への上乗せ関税も発表しており、中国産原材料の加工品への扱いは不透明です。中国商務部はベトナムが中国の利益を損なう合意をすれば対抗措置を講じると警告しています。
7月4日:4.5兆ドル規模の減税法案成立
独立記念日に、トランプ大統領は米議会上院を通過していた4.5兆ドル規模の減税法案に署名し、成立させました。この法案には5兆ドルの連邦政府債務上限引き上げも含まれています。
この減税により、連邦財政赤字は今後10年間で3.4兆ドル拡大すると試算されています。興味深いことに、イーロン・マスク氏はこの減税法案を「破滅的だ」と酷評し、新党結成を示唆するなど激しく批判しています。
減税法案は目先の資金繰りリスクを解消する一方で、連邦政府債務の拡大につながり、米国債の安定消化に懸念を生じさせる可能性があります。トランプ政権発足後、「ドル離れ」が取り沙汰されており、財政面を念頭に置いた「ドル離れ」が意識される状況となっています。
7月7日:BRICS同調国への関税措置示唆
トランプ大統領は、BRICSの反米政策に同調する国々に対し、追加で10%の関税を課す可能性に言及しました。これにより、対新興国通貨を中心にドル買いが進み、ドル/円にも影響が波及しました。
この発言は、トランプ政権の「アメリカ・ファースト」政策が、中国だけでなく新興国全体を対象とした包括的な保護主義政策であることを示しています。
7月8日:対日25%追加関税の通告 – 日本にとって最も重要な発表
トランプ大統領は、日本からの輸入品に対して8月1日から25%の追加関税を課すと通告しました。これは日本だけでなく、以下の国・地域も対象となっています:
- セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ
- インドネシア、韓国、カンボジア、タイ、バングラデシュ、マレーシア、ミャンマー、ラオス
- カザフスタン
- チュニジア、南アフリカ共和国
- 欧州など
トランプ大統領は、日本がコメ不足にもかかわらず米国産コメを輸入しないことや、日本の対米自動車輸出に対して米国からの輸入が少ないことが「公平ではない」と批判しており、30〜35%の関税率引き上げも辞さない構えを示しています。
さらに、来年5月に任期満了を迎えるパウエルFRB議長の任期よりもかなり前に、次期議長を指名する可能性を示唆しています。これは中央銀行の独立性を脅かす動きとして懸念されています。
世界経済への多面的な影響
関税政策がもたらす市場の大混乱
トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」や「取引重視」の政策は、世界経済に大きな不確実性をもたらしています。
2025年前半のマーケット動向:
- トランプ大統領の関税政策への不信感から世界の投資家がアメリカ離れを起こし、米ドルが独歩安となりました
- 資金はアメリカからヨーロッパにシフトし、スウェーデンクローナ、スイスフラン、ユーロ、ノルウェークローネ、英ポンドといった欧州通貨が強くなりました
- 新興国への資金流入が加速しており、MSCI新興国通貨指数が過去最高を更新しています
関税によるコスト上昇に直面する企業の約75%が、その一部を顧客に転嫁すると回答しており、これにより実質所得の悪化や個人消費への下押し圧力が懸念されています。
4月初めに発表された米国相互関税は想定以上に厳しい内容であり、市場は大きく反応し、日米欧の株式市場は急落しました。これは、自由貿易体制を否定する内容として市場に衝撃を与えました。しかし、関税上乗せ分が90日間停止され、通商交渉への楽観的な見方も浮上し、5月初めには急落前の水準まで回復しました。
関税交渉は7月9日に期限を迎え、合意に至らなければ市場のボラティリティが一段と高まる可能性があります。
財政政策とドル離れの加速
米議会で可決された大型減税法案は、目先の資金繰りリスクを解消する一方で、連邦政府債務の拡大につながり、米国債の安定消化に懸念を生じさせる可能性があります。
関税政策は「モノの貿易」に注目されがちですが、日米間、米EU間ともに「サービス貿易」の比重が高まっており、サービス貿易ではアメリカが対日、対EUともに黒字であるため、経済の全体像はより複雑になります。
地政学リスクの高まり
イスラエルとイランの間では一時的に小康状態が続いていますが、停戦が短期で終わる可能性も懸念されています。ウクライナ危機発生から2年以上が経過し、国際エネルギー情勢は一時落ち着きを取り戻したものの、原油価格は約80ドルを中心とした高い水準で推移しており、地政学リスクが依然として価格上昇要因となり得ます。
中国は不動産不況による内需低迷が継続しており、「デフレ輸出」の構図が指摘されています。南アフリカの通貨ランドは対米ドルで減価傾向にありますが、金融政策への信認は高いとされています。ブラジルレアルは、ブラジル中央銀行の度重なる利上げにより、政策金利が2006年以来の高水準(15%)となり、対ドルで上昇を続けています。
日本経済への深刻な影響
GDP押し下げと企業への影響
トランプ関税は日本経済にとって重しとなることが懸念されており、今後の展開が注目されています。関税による悪影響は「これから」であり、トランプ関税による追加関税全体で日本のGDPを0.85%押し下げるとされています。
日本企業を対象とした調査結果:
- 短期的な影響(今後1年以内):「マイナス影響がある」と回答した企業が40.7%
- 中長期的な影響(今後5年程度):「マイナス影響がある」が44.0%に増加
- 「分からない」と回答:38.5%(強い不透明感を示す)
米国の関税引き上げの影響は、2025年後半に実体経済に表出すると見られています。特に7月から9月期には外需が弱まり、日本経済は浅いマイナス成長に陥る公算が大きいと予想されています。
具体的な企業への影響
懸念事項:
- 自動車など主要産業の国内生産減少による需要減
- 米国への進出計画の取り止め(化学品製造や機械製造企業で実例あり)
- 中小零細企業の行き詰まり(すでに大きな影響を受けており、行き詰まっている企業も多い)
- 製造業における売上予測の困難さ(輸出が困難になり、生産減少傾向)
- 物価高による消費の落ち込み
- 大手企業による設備投資の見送り
- 急な方針変更による予測不能性
加工業種(大企業)の2025年度経常利益計画は、関税への警戒感から前回比で7.1%ポイントも下方修正されており、トランプ関税の悪影響が今後顕在化する可能性が指摘されています。
交渉が長期化すれば、日本企業による「値上げ回避」戦略も限界を迎え、価格転嫁が進めば米国のインフレが再加速し、回避すれば国内の下請け企業にしわ寄せが及ぶと見られています。
限定的・プラス影響:
- 国内で生産する農産物販売会社は輸入品が届きにくくなるメリット
- 不動産や国内向けサービス業(娯楽サービスなど)には直接的な影響なし
- トランプ関税は最終的に米国民が負担するため適正化に向かうとの見方も
株式市場への影響
日経平均株価は40,000円近くまで回復した後、7月から9月期はグローバル市場の「米国離れ」というプラス材料と、日本を含むグローバル景気の減速というマイナス材料が相殺する形でレンジ相場に入ると見られています。
しかし、10月から12月期には日米両国経済に底打ち感が見られ始め、日本株市場は米国株市場と同様に上昇局面入りすると予想されています。日本株は内需の回復という日本独自の好材料が存在するため、今年後半は米国株市場を上回るパフォーマンスを示す可能性も指摘されています。
国内の物価高対策と賃金動向
日本の実質賃金は2025年5月時点で5カ月連続のマイナスとなっています。しかし、10月から12月期にはインフレ率が2~2.5%に低下し、春闘による賃上げと合わせて実質賃金がプラス化し、内需が回復すると見込まれています。
政府の物価高対策:
- ガソリン価格の定額補助(最大10円/リットル)を継続実施
- コメ価格の安定化のため備蓄米の放出(全国平均価格は3691円まで下落)
- 電気・ガス代について、7月から9月使用分に補助を実施(特に冷房使用が増える8月は補助額を引き上げ)
- 標準家庭で3カ月間に計3000円程度の引き下げ効果が見込まれる
公明党はこれらの物価高対策を強く推進したと表明しています。減税には時間がかかるため、税収の上振れ分を使って現金給付を行い、減税の恩恵を受けにくい子どもや住民税非課税世帯を重点的に支援する方針が示されています。
金融政策への影響
日本銀行は、2025年7月1日に就任した増審議委員のコメントからも、日米関税交渉の不確実性が予断を許さない状況であり、「利上げを急ぐ状況でない」との見解が示されています。
高田審議委員は、米国の関税政策を「関税台風」と例え、利上げを一時休止する局面であるとの見解を示しました。企業設備投資や賃上げに底堅い動きが続いていることから、次の利上げに向けては前進したとの認識を示しつつも、海外環境の不確実性が大きく、利上げの時期については言及を避けています。
日銀は、トランプ関税の影響を見極めながら、不確実性が薄らいだ後にどこかで追加利上げを再開する方針を模索していくと見られています。2025年末から2026年初めにかけて追加利上げの時期を検討する可能性も指摘されています。
家計の投資意欲への影響
6月の投資信託経由の対外証券投資は、新NISA開始後も控えめな動きが続いています。これはトランプ関税を巡る不透明感が投資意欲を阻害しているためであり、家計部門の投資意欲は膠着状態にあります。
石破政権の対応と参院選への影響
石破首相の対応と支持率低下
トランプ大統領の対日25%関税通告に対し、石破首相は「誠に遺憾」としつつ、実質的には関税率据え置きであり、協議期限の延長だと指摘しています。国際情勢が大きく変動する中で、石破首相の外交能力の欠如が「致命的な欠陥」となりうるとの見方も存在します。
石破内閣の支持率は32.8%に下落しており、その要因として以下が挙げられています:
- 経済政策への不満
- 社会保障政策への期待外れ
- 外交政策の不手際
- 安倍派の裏金事件に関する検察審査会の「起訴相当」議決など、政治と金の問題
日米間の関税見直し交渉は長期化の様相を呈しており、日本は米国との通商協議の優先権を失い、「後回し」になっている状況です。赤沢大臣と米国のベセン財務長官との協議はできていません。
第27回参議院選挙と各党の政策
7月3日に公示された第27回参議院選挙では、物価高対策やトランプ関税への対応が主要な争点となり、与党が過半数を維持することは極めて困難な情勢であると報じられています。
主要政党の政策と動向:
自由民主党:
- 石破総理は1人2万円の現金給付(外食・酒を除く食費の物価上昇分に相当)を掲げるが、6月の調査では7割の人がこれを評価していない
- 消費税の減税については、法律やシステムの変更に時間がかかり、富裕層ほど恩恵が大きいという疑問を呈している
- 外国人運転免許や不動産所有問題への対策を訴え、保守層の支持をつなぎ止めようとしている
公明党:
- 参議院選挙の重点政策として「減税と給付による生活応援」「現役世代の所得増加」「社会保障の充実」「安全・安心な日本」「国際社会の平和と安定」の五つの柱を掲げる
- 出産育児一時金の増額(50万円へ)、ガソリン・コメ価格の値下げ、電気・ガス代補助、政策活動費の廃止、高額療養費制度の見直し凍結などを「主な実績」としてアピール
- 7選挙区での全員当選と比例区で7議席以上(合計14議席以上)の獲得を目指し、厳しい選挙戦を戦っている
- 低所得者や子育て世帯向けの家賃補助制度の創設も掲げる
立憲民主党:
- 「政権交代こそ最大の政治改革」を掲げる
- 野田代表は、米政策に演説の半分を費やし、食料品への消費税を0%にすることを訴えた
国民民主党:
- 「手取りを増やす政治」を看板政策として訴える
- 東京都議選では大きく議席を伸ばした
- 大躍進は「忘れられた人々」の声を直接政策に反映した「ハイブリッド型ポピュリズム」が要因と分析
- 防衛力強化や防衛費拡充には賛成だが、国内防衛産業の育成を重視
- アクティブサイバーディフェンス法案の成立、人材育成、スパイ防止法、外国人土地取得規制の強化、エネルギー自給率の向上(原発新設)も主張
参政党:
- 「日本人ファースト」を掲げる
- 「自国は衰退している」「既存の政党や政治家は自分たちを気にかけていない」と感じる層からの支持
- トランプ関税に対しては、国内の自動車関連税の見直しと自動車産業への政府支援を求める
れいわ新選組:
- 山本代表は、物価高対策や消費税の廃止を強く訴える
- トランプ関税に対しては、東南アジアや「グローバルサウス」の国々とグループで交渉に臨むべきだと提言
- 通商交渉に農業を持ち出すこと(特にコメの開放)に反対
日本共産党:
- 消費税の廃止を目指し、緊急に5%への減税を掲げる
- 政府の防衛費増額も批判
日本保守党:
- 物価高対策を最も訴える一方、外国人政策にも重点を置く
社会民主党:
- 「ミサイルより暮らしを、ミサイルより平和を」を掲げ、防衛費の予算配分に異議を唱える
日本国民の意識と政治への不信感
世論調査会社イプソスの「ポピュリズムレポート2025」(2025年6月18日発表)によると、日本人の意識に深刻な変化が見られます:
- 日本人の70%が「自国は衰退している」と感じている(調査対象31カ国中3番目に高い数値)
- この悲観的な見方は9年間で約1.8倍に増加
- 日本人の68%が「既存の政党や政治家は、私のような人間を気にかけていない」と感じている
- 2016年の39%から大幅に増加
- 特にコロナ禍を経て政治への期待感が回復していない状況
若者の投票率は特に20代で20%を下回るなど低く、政治との距離が課題となっています。若者からは、政治が複雑で分かりにくい、具体的な問題解決が進んでいない、という声が聞かれます。しかし、政治に興味がないわけではなく、経済対策や、外国人増加に伴うトラブルへの懸念から「日本人ファースト」のような意見にも関心があります。
6月の東京都議選では、自民党が大敗し、公明党も全員当選とはいかないなど、与党は苦戦しました。一方で、国民民主党は「手取りを増やす」をスローガンに掲げ、大きく議席を伸ばしました。
地方自治体の取り組み – 中野区議会の事例
中野区議会では、2025年2月の定例会で、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」を控え、地域包括ケアシステムの強化や、誰も取り残さない相談支援体制の構築が議論されました。
区長の認識と対応:
- 実質賃金が物価上昇に追いついていない現状を認識
- 生活困窮者への支援の必要性を認める
- 低所得世帯へのエアコン購入費助成の検討
- 年末年始の長期休暇中の相談会設置の検討
その他の施策:
- 大学進学に向けた区独自の給付型奨学金制度の創設(2025年度に全庁的な検討体制で進める予定)
- 会計年度任用職員の公募によらない再度任用の上限回数を撤廃し、安定的な人材確保を図る方針
日米同盟と外交・安全保障への影響
米国の対日コミットメントの揺らぎ
米国の対日防衛コミットメントには3つのシナリオが考えられており、日本は現在第一と第二の中間あたりにいると認識されています:
- 従来通りの堅持
- 台湾は不明だが日本は重要
- 日本へのコミットメントも不明瞭になる
トランプ政権は、ヨーロッパがアメリカに安全保障をただ乗りしているという意識が根強く、軍事的関与を基本的に削減する方向です。米国は欧州から撤退し中国・インド太平洋に焦点を当てる方針ですが、これは日本への防衛コミットメントの揺らぎにもつながる可能性があります。
日本の対応戦略
日本は、米国が「インド太平洋、アジア、そして日本の平和と繁栄は、アメリカの平和と繁栄に直結している」と認識するようあらゆるレベルで努力する必要があります。防衛力強化、日米防衛協力の深化を通じて米国を巻き込み、中国や北朝鮮に米国を切り離せると思わせない戦略が重要です。
経済的にも日本が不可欠なパートナーであると認識させ、同盟の価値を再発見してもらうための新しい枠組み構築が求められています。日米同盟は「目的」ではなく「日本の国益を守るための手段」であるという原点に立ち返るべきと提言されています。
中谷防衛大臣は、インド太平洋諸国との防衛協力・連携を進める「OCEAN構想」(開放性、包摂性、透明性、ルールに基づく国際秩序回復など)を提唱しました。日米豪印共同訓練「マラバール」などのアジア太平洋を基軸とした多国間協力の推進が期待されています。
米国への信頼低下という深刻な問題
トランプ関税が「グローバルサウス」諸国を敵に回し、米国への信頼が一気に崩壊していることが日本の国益にとっても大きな懸念です。米国への信頼を失った国々が中国やロシアに魅力を感じる土壌が広がっています。
日米同盟が日本の「資産」ではなく「負担」になりかねない可能性も指摘されており、日本はこれを米国に伝える必要があります。ヨーロッパでは動揺が広がっており、アメリカに見捨てられる可能性を危惧する声があり、「プランB」のような自立の議論が日本よりもリアリティを持って語られています。
ウクライナ支援の一時停止を受け、欧州は米国に頼り続けることができないという意識が高まり、自らの将来を米国とロシアに決められたくないと考えています。英国とフランスが安全保障のための部隊派遣を進めるなど、欧州の戦略的自立に向けた新しい動きも出ています。
エネルギー政策と経済安全保障
日本のエネルギー政策は、ウクライナ戦争の長期化、台湾情勢、米国大統領選挙の結果による政策転換(LNG輸出許可の一時停止など)といった地政学リスクに大きく左右される状況にあります。
原子力の活用に関する議論
- 日本は原子力技術と優秀な人材を持つが、それが活用されていない「宝の持ち腐れ」だと指摘
- 国民の原子力に対する不安(科学的な安全と心理的な安心の混同)や、メディアによる不安煽りが問題視
- 高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の処分場建設は、原子力利用国の共通課題
- 老朽化した火力発電所の事故リスクや燃料供給の問題も指摘
- 義務教育でのエネルギー問題の教育の必要性も提言
再生可能エネルギーと化石燃料
- カーボンニュートラルの実現とエネルギー安全保障の強化には、生産、送電網、省エネを含む包括的なコンセプト設計と国際協力が必要
- 太陽光、風力、地熱、水力発電などの再生可能エネルギーに加え、eメタン/合成天然ガス、バイオガス、CO₂回収、原子力、蓄電池、低炭素水素、アンモニアなど多様なソリューションが利用可能
- 天然ガスはエネルギートランジションにおいてエネルギー安全保障に重要な役割を担い、特に東南アジアでのLNG需要が急増
- 米国産LNGの安定供給は、地域の経済成長と米国のプレゼンス強化に寄与すると期待
今後の展望と課題
トランプ政権の関税政策は、戦後の自由貿易体制の秩序を根底から覆すような保護主義的、単独行動主義的な政策として批判されています。この関税政策は一時的に大きな波紋を呼んでいますが、国際経済秩序がどう変わるかは、今後の交渉次第で何がどこまで解除され、何が残るかを見極める必要があります。
関税賦課による政策の不確実性自体が企業の設備投資意欲を減退させ、景気の重しとなる可能性があります。アメリカ国内で物価が上昇し、共和党議員の地元の産業が報復関税で打撃を受ければ、政治的な反動が出てくる可能性もあります。
日本にとっては、国益を守りつつ、日米双方の利益となるような合意を目指して交渉を続けることが重要です。同時に、国内では物価高対策と実質賃金の改善が急務となっており、政府の対応が注目されます。
世界的な分断の深刻化(米中対立や西側と中ロの対立など)は、経済安全保障を含む総合的安全保障の重視をもたらしています。日本は単独で中国に対処することが物理的に困難であり、米国との同盟関係を維持しながらも、多国間協力を推進し、リスクを分散する戦略が求められています。
この調査結果は、トランプ政権の政策が国内外の経済に多大な影響を与えていること、特に貿易政策が日本企業の業績や投資意欲に不透明感をもたらしていることを示しています。また、日本国内では物価高騰と政治への不信感が国民の間に広がり、今後の政局にも影響を及ぼす可能性があります。
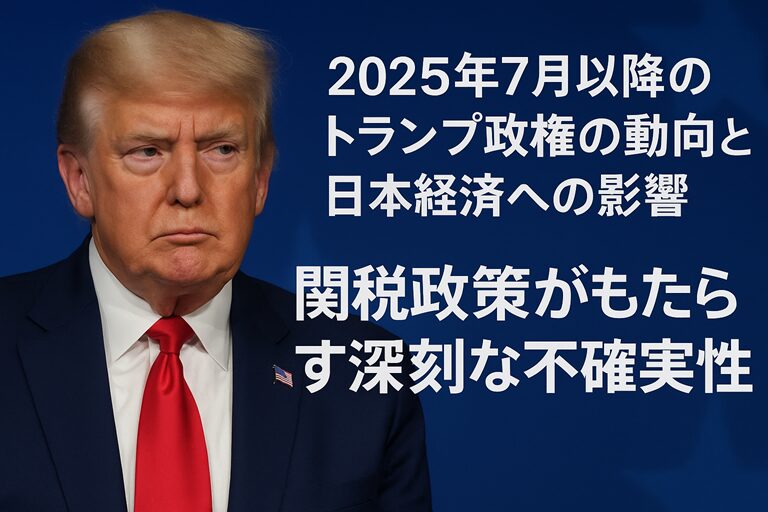

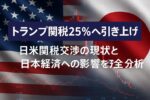

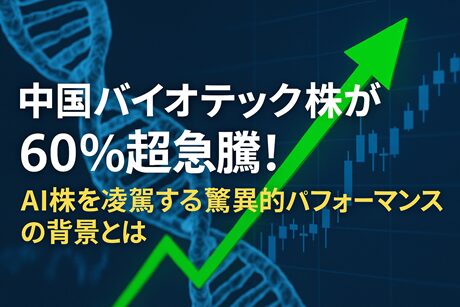








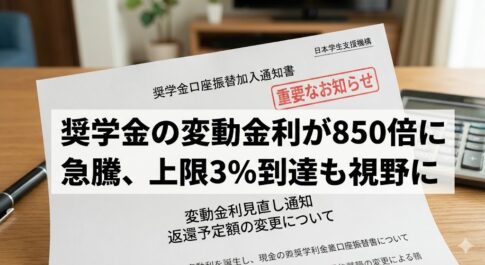
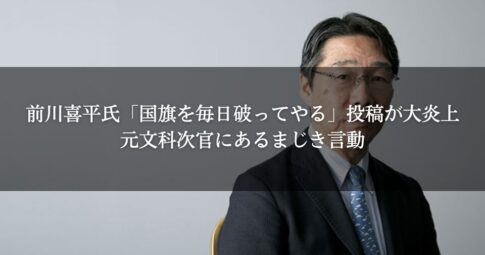






コメントを残す