目次
地球の自転が異常加速、1日が短くなっている理由とは?マイナスのうるう秒導入の衝撃
2025年7月10日、地球の自転速度が観測史上今年最も速くなり、この日の長さが標準的な24時間よりも1.38ミリ秒短かったことが、国際地球回転・基準系事業(IERS)および米海軍天文台の観測によって明らかになりました。7月9日、7月22日も短縮傾向にあり、8月5日にも歴史的に短い1日になると予測されています。
重要:この現象は一時的なものではありません。米海軍天文台の天文学者ニコラス・スタマタコス氏によると、過去10年間で1日の平均的な長さはおおむね短くなっており、特に過去5年間はその傾向が顕著だと指摘しています。2020年以降だけで、1日の長さが標準より短い日が28回も観測されており、これは「明らかに異常な頻度」です。
原子時計で明らかになった地球の自転の真実
地球の自転速度とは、地球が自転軸を中心に1回転するのにかかる時間で、およそ8万6400秒(24時間)とされています。しかし、この数値はあくまで平均的なものであり、実際には常に変動しています。
原子時計による正確な1日の計測が始まったのは1955年以降です。原子時計は、原子が発するスペクトルを周波数基準として利用する装置で、原子・分子またはイオンが持つ離散的エネルギー間隔が一定不変であるという原理に基づいています。
原子時計の進化
- 1955年:最初のセシウム原子時計が英国で開発(精度:約100億分の1)
- 1967年:秒の定義がセシウム原子の遷移周波数に基づく表記に変更
- 現在:セシウム原子時計の誤差は1京分の1秒程度まで進歩
- 次世代:光格子時計(2001年に東京大学の香取秀俊教授が提案)は18桁の性能に到達
観測史上最短の1日の記録更新が続く異常事態
近年の地球の自転速度加速は、まさに前例のない現象です。
最近の主要な記録
- 2020年7月19日:通常より1.47ミリ秒短い(当時の最短記録)
- 2022年6月29日:1.59ミリ秒短縮(原子時計導入以来の最短記録を更新)
- 2024年7月5日:1.66ミリ秒短縮(史上最短の1日)
- 2025年7月10日:1.38ミリ秒短縮(2025年最短)
「2020年は、1970年代の記録開始以降で最も自転が速かった年とされています。長期的には月の潮汐力によって自転速度は遅くなる傾向にあるにもかかわらず、ここ数年の急激な自転速度の加速は、歴史的に異常であると科学者たちは認識しており、その明確な原因を特定できずに困惑しているのが現状です。」
地球の自転速度が変化する複雑なメカニズム
地球の自転速度は、地球を構成する様々な要素(固体地球、液体核、海洋、大気、氷床など)間の複雑な相互作用と、月や太陽などの外部天体からの影響によって変動します。これは地球の自転角運動量保存の法則に基づいており、一部の質量分布が変わると、それを補うように他の部分の回転速度が変化します。
1. 月の引力と潮汐摩擦 – 長期的な減速の主因
地球の自転が徐々に遅くなっている主要な原因は、月の引力による「潮汐摩擦」です。地球が月の公転速度よりも速く自転しているため、月の重力が地球に「ブレーキ」をかけるように作用します。
潮汐摩擦の影響
- 海水と海底との摩擦により発生(海洋潮汐トルク)
- 月は毎年数センチメートルずつ地球から遠ざかる
- 月形成直後:地球から2.4万km(現在は約38万km)
- 当時の1日:わずか5時間
- NASAによると100年ごとに2.3ミリ秒ずつ減速
- 1億8000万年後には1日が25時間になる予測
2. 「退屈な10億年」と熱潮汐トルク
興味深いことに、約20億年前から約10億年前までの「退屈な10億年」と呼ばれる期間は、海洋潮汐トルクと熱潮汐トルクが釣り合い、地球の自転周期が約19時間でほぼ固定されていたことが研究で明らかになっています。
太陽からの「熱潮汐トルク」は、太陽によって大気中の水蒸気やオゾンが加熱され、大気が膨張することで起こります。この効果は海洋潮汐トルクよりも弱いものの、地球の自転を加速させる方向に働くとされています。
3. 地球内部の核の運動 – 最近の加速の鍵?
最新の研究:地球内部の液体核が過去50年近くにわたって回転速度を落としており、その運動量の保存を補う形で、その上部にある固体部分(地殻やマントル)が逆に加速している可能性が指摘されています。
地球の内核の運動変化が自転速度に影響を与えると考えられており、流体核とマントルの結合状態も、自転速度変動に関する情報を提供します。マントルと流体核が異なる軸の周りに自転することで、核マントル境界面を通じて互いにトルクを及ぼし合うことがあります。
この「核の遅れ」が、最近の急激な自転加速と無関係ではないと多くの科学者は見ていますが、「なぜ今、これほど急に核のスピードが変わっているのか」は完全には解明されていません。
4. 大気と海洋の運動
地球の大気や海洋も地球と一緒に回転しており、これらの運動の変化が地球全体の自転速度に影響を与えます。
大気・海洋の影響
- ジェット気流:夏に弱まると地球本体の自転が速まる
- 気象現象:エルニーニョ・ラニーニャ現象も影響
- 角運動量交換:大気と固体地球の間で運動量を共有
- 相関性:気象学的観測と測地学的観測がよく一致
5. 地球上の質量分布の変化
地球の質量分布が変化すると、フィギュアスケート選手がスピンする際に腕を縮めたり伸ばしたりして回転速度を調整するのと同様に、地球の自転速度も変化します。
気候変動の影響:スイス連邦工科大学チューリッヒ校の研究では、気候変動が進んだことで氷の融解や地下水の移動が起こり、100年で数ミリ秒のペースで1日が長くなっていることが判明しています。
2011年の東日本大震災では、地球の質量分布が変わり、1日の長さが1.8マイクロ秒(0.0000018秒)短くなったと報告されています。
地球の自転速度の歴史的変遷
地球の自転速度は、その誕生以来、劇的に変化してきました。
地球の1日の長さの変遷
- 約10億~20億年前:1日はわずか19時間ほど
- 約4億3000万年前:化石化したサンゴの分析から、1日が約21時間であったことが判明
- 恐竜時代(7000万年前):1日は約23.5時間、1年は372日
- 現在:1日は24時間(正確には23時間56分4秒)
- 1億8000万年後(予測):1日は25時間になる可能性
これらの過去の記録は、サンゴや貝殻の化石の成長線(木の年輪のように、サンゴや貝の成長に伴って一日や一年に対応する線ができる)を調べることで推定されています。貝は炭酸カルシウムを分泌することで日々貝殻に層を形成するため、殻の層の薄さから1日が短かったと類推できます。
最先端の観測技術:VLBIと宇宙測地学
明治時代の地球回転変動の観測は光学望遠鏡を用いた目視観測でしたが、現在では電波望遠鏡を用いた干渉計(VLBI:超長基線電波干渉計)に代表される宇宙測地技術が主流となっています。
VLBI技術の特徴
- 複数の電波望遠鏡を組み合わせて遠方の電波星からの電波を同時受信
- 観測局ごとの受信電波の位相差から地球の向きを精密に割り出す
- 従来の光学観測より2桁高い1ミリ秒角の精度
- 地球の姿勢を極めて正確に決定可能
その他の精密地球計測技術として、体積ひずみ計(地下の体積変化を測定)、検潮所(海面高の変化を測定)、地震波トモグラフィー(マントルの不均質構造から対流を推測)なども使用されています。
史上初の「マイナスのうるう秒」がもたらす危機
地球の自転速度が原子時計による時刻(国際原子時:TAI)とずれが生じた場合、そのずれを調整するために「うるう秒」が導入されます。これまでは地球の自転が遅れる傾向にあったため、1972年以降、合計27回の1秒を追加する「正のうるう秒」が挿入されてきました。
緊急警告:近年地球の自転が加速しているため、原子時計の方が進んでしまい、世界で初めて「負のうるう秒」、つまり1秒を削除する調整が必要になる可能性が出てきました。この「マイナスのうるう秒」は、早ければ2029年までに導入される可能性があると予測されています。
マイナスのうるう秒の実施方法:
日本時間では午前8時59分58秒の次が午前9時00分00秒となり、午前8時59分59秒が削除されることになります。これは過去に前例がなく、世界中のITシステムに壊滅的な影響を及ぼす危険性があると警鐘が鳴らされています。
過去のうるう秒によるシステム障害事例
過去の「正のうるう秒」の調整でさえ、以下のような深刻な問題が発生しています:
実際に発生した障害
- Linux・Reddit:システムで不具合が発生
- 航空業界:搭乗予約システムがダウンし、フライトに影響
- GPS:精度低下(ミリ秒単位の正確な時間情報に依存)
- 金融システム:誤作動(秒単位の正確な時刻同期が不可欠)
「Meta、Google、Amazonのような巨大IT企業は、『負のうるう秒』の導入に強く反対しています。多くのシステムは時間の追加には対応できていても、時間の削除に対応できる設計になっていない場合があるためです。」
うるう秒廃止への国際的な動き
これらの懸念を受けて、国際度量衡総会(CGPM)は2022年に、2035年までにうるう秒の調整を停止する方針を採択しました。これは実質的な「うるう秒の廃止」を意味します。
うるう秒廃止後の代替案
- 許容される時刻のずれの範囲を広げる
- 「うるう分」の導入を検討
- 「うるう時間」の導入を検討
- 他の定義の改定等多くの調整が必要
なお、「うるう年」は地球の公転周期と暦のずれを調整するためのものであり、「うるう秒」とは全く異なる仕組みです。うるう秒が廃止されても、うるう年がなくなることはないとされています。
月の位置変化による短期的な影響
長期的な減速要因である月の引力ですが、短期的な視点では、月の公転軌道上での位置の変化も地球の自転速度に影響を与えます。
月が地球の赤道から最も離れた位置(極に最も近づく)にある時、月の重力が地球の自転軸に及ぼす影響が変わり、自転がわずかに速くなることがあります。2025年7月9日、7月22日、8月5日に予測されている自転速度の加速も、このような月の位置関係が影響している可能性があります。
人間活動が地球の自転に与える影響
「人間は、私たちが認識している以上に大きな影響を地球に与えており、当然ながら、人間には地球の未来に対して大きな責任が課せられている」
気候変動による氷河の融解や地下水の移動は、人間活動が間接的に地球の自転速度に影響を与えていることを示しています。これは、地球の自転速度の変化が、私たち人類の活動が地球システム全体に与える影響の大きさを示す象徴的な事例でもあります。
日常生活への影響と時間の概念
1日の長さがミリ秒単位で変化しても、私たちの日常生活でそれを体感することはまずありません。目の瞬きが100〜400ミリ秒かかるのに対し、1日の短縮はわずか1ミリ秒程度だからです。
しかし、天文学、通信、精密工学などの分野では、このようなわずかな誤差も大きなエラーにつながるため、無視できない重要な問題とされています。
長期的な影響:もし地球の自転と時刻のずれが調整されなければ、はるか未来には日が昇る時間が変わってくる可能性があります。1世紀で1分、1000年で10分、6000年後には1時間も日の出の時刻がずれてしまうという試算もあります。
地球の内部構造が明かす自転の謎
地球の内部構造は、その回転挙動を理解する上で不可欠です。
地球内部の特徴
- 慣性モーメント係数:約0.33(地球半径の半分を占める金属核の存在を反映)
- マントルの粘性:上部マントル10^20 Pa・s、下部マントル10^22 Pa・s
- 地震波異方性:内核内部の鉄の結晶粒子の配列により発生
- マントル対流:長期的には「流体」として振る舞い、プレート運動を引き起こす
マントルは長期的な時間スケールでは「流体」として振る舞い、熱対流を起こしています。このマントル対流の表層部分の動きがプレート運動に他なりません。地震波が核を通過する際、その向きに依存して大きく変化する「地震波異方性」という現象も観測されています。
まとめ:変化し続ける生きた惑星
地球の自転速度の変化は、月の引力、大気と海洋の動き、そして地球内部のダイナミクスという、複数の複雑な要因が絡み合って生じています。長期的には月の潮汐力によって遅くなる傾向にある一方、近年では地球内部の核の運動や大気の変動などの影響で、一時的に加速する現象が観測されています。
結論:2020年以降の急激な自転速度の加速は、科学者たちも明確な原因を特定できておらず、困惑しているのが現状です。この異常な加速により、史上初の「マイナスのうるう秒」導入の可能性が現実味を帯びてきました。現在の技術の精密さゆえに生じたこの新たな課題に対して、継続的な観測と適切な対策が求められています。
地球の自転速度の変動を理解することは、地球深部の構造や気候変動との関連性、さらには太陽系の他の天体の進化を解明する上でも重要な意味を持っています。
私たちの住む地球は、常に変化し続ける、謎に満ちた生きた惑星なのです。
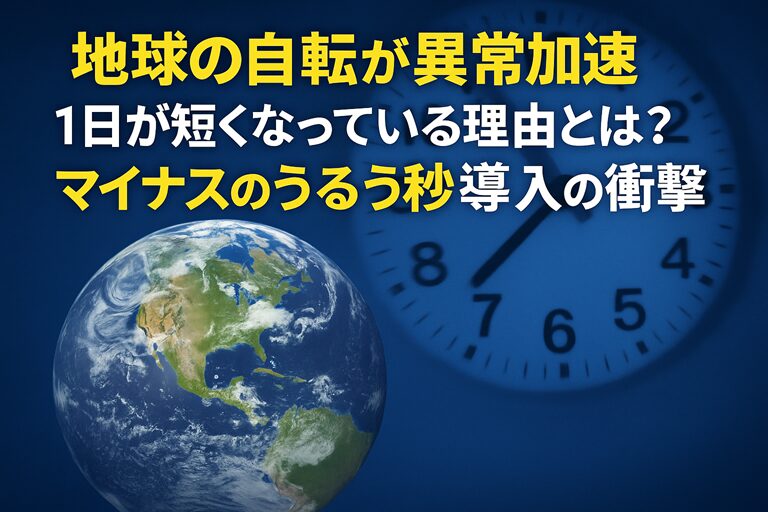




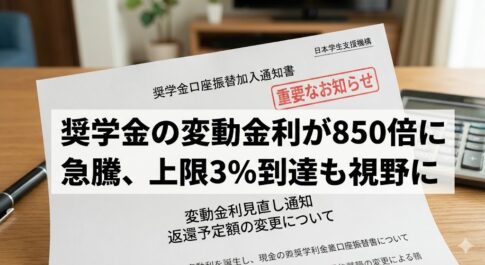
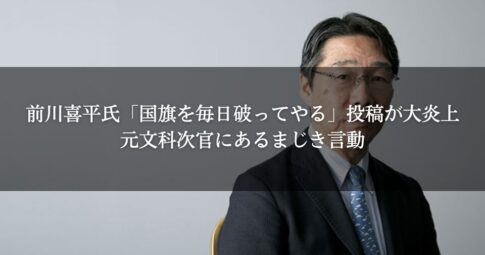






コメントを残す