目次
- 1 ベッセント米財務長官の衝撃発言:FRBは「凍り付いている」- 米国経済政策の転換点を徹底分析
- 1.1 ベッセント財務長官の主要発言とその背景
- 1.2 2022年のFRBショック – 積極的すぎた金融引き締めの代償
- 1.3 イールドカーブが示す経済の不安定性
- 1.4 米国債市場の構造的問題と財政リスク
- 1.5 FRB議長人事を巡る政治的駆け引き
- 1.6 トランプ政権の政策がもたらす不確実性
- 1.7 FRBの将来の利下げ見通し – 専門家の予測は分かれる
- 1.8 世界経済への波及効果
- 1.9 米国の「不確実性の震源地」化
- 1.10 財政構造の問題と社会保障
- 1.11 信用格付け会社の役割と限界
- 1.12 債券市場の基礎知識 – 投資家が理解すべき重要概念
- 1.13 投資家への示唆 – 今後の市場展望
- 1.14 まとめ – 転換期にある米国金融システム
ベッセント米財務長官の衝撃発言:FRBは「凍り付いている」- 米国経済政策の転換点を徹底分析
2025年、米国経済は重要な転換点を迎えている。ベッセント米財務長官がブルームバーグテレビジョンとのインタビューで語った内容は、単なる政策批判を超えて、米国の金融システムが抱える根本的な問題を浮き彫りにした。「FRB当局者はハンドルを握りながら凍り付いているようだ」という衝撃的な表現は、金融市場に大きな波紋を広げている。
ベッセント財務長官の主要発言とその背景
ベッセント財務長官は、現在の米国債利回り水準を踏まえると、政府が長期債の発行を増やすのは理にかなっていないと示唆した。長官は「長期債の増額発行は2021年や2022年にしておくべきだったことだ」と述べ、その必要はないだろうとの見方を示している。
これは興味深いことに、自身の前任者であるイエレン財務長官が短期債への依存を強めていると批判していたにもかかわらず、ベッセント氏自身も財務長官就任後はイエレン氏の国債発行戦略を継承していることを意味する。
長官は、年末までの10年債利回り水準について、多くの要因に左右されるとしつつも、インフレの鈍化に伴い、イールドカーブ(利回り曲線)全体が平行してシフトダウンする可能性があると考えていると述べた。
FRBへの痛烈な批判
金融政策については、ベッセント長官はFRB当局者が「ハンドルを握りながら凍り付いているようだ」と表現した。そして、「2022年に国民を失望させたことから、FRBは足元ばかりを見ており、前を向いていないことが懸念される」と述べ、FRBの過去への固執が問題であるとの見解を示している。
2022年のFRBショック – 積極的すぎた金融引き締めの代償
ベッセント長官のFRB批判の背景には、FRBが2022年以降に行った金融引き締め策とその影響がある。この時期のFRBの行動を詳細に見ていこう。
急激な利上げの経緯
FRBは2022年3月から利上げを開始し、わずか2年弱の間に政策金利を5%引き上げた。この急激な政策転換の具体的な経緯は以下の通りである:
- 2022年3月:利上げ開始
- 2022年6月:予想外に上昇した5月の消費者物価指数(CPI)を受けて、0.75ポイントの利上げを決定。これは27年7カ月ぶりの引き上げ幅であった。2022年末の見通しは3.4%と大幅に上方修正された
- 2022年9月:3会合連続で0.75%の利上げを決定し、FF金利の誘導目標は3.00%~3.25%に引き上げられた。この時点で、2022年末の政策金利見通しは4.4%に、2023年末は4.6%に大幅に上方修正された
量的引き締め(QT)の同時進行
FRBは、大規模に購入した米国債などを圧縮する量的引き締め(QT)も実施した。ピーク時の約9兆ドルから2025年2月12日時点で6.81兆ドル余りまでバランスシートを縮小している。この大規模な資産圧縮は、金融市場の流動性を急速に吸収し、市場に追加的な圧力をかけた。
インフレ認識の転換
パンデミック以降、米国のインフレ率はFRBの予想を大きく上回り、かつ根強いものとなった。個人消費支出(PCE)価格指数はFRBの中位予測を大幅に上回って上昇した。
2021年11月、パウエルFRB議長はついにインフレを一時的なものと見なすのをやめ、2022年には積極的に政策金利の引き上げを開始した。FRBは、物価上昇率を目標の2%に戻すことに強く注力していると表明している。
イールドカーブが示す経済の不安定性
ベッセント長官が言及したイールドカーブの動向は、金融市場や景気見通しを読み解く上で極めて重要である。イールドカーブとは、債券の償還期間と利回りの関係をグラフにしたもので、将来の金利や経済状況を予測する上で重要な指標となる。
イールドカーブの基本概念
イールドカーブは、通常、残存期間が長くなるほど利回りが高くなる「順イールド」の右上がりの曲線になる。これは、期間が長いほど価格変動などのリスクが高まるため、投資家が高い利回りを要求するからである。
「逆イールド」とは、満期までの期間が短い債券の利回りが、長い債券の利回りを一時的に上回る逆転現象である。この現象は一般に「景気後退(リセッション)の予兆」と解釈される。
歴史的な逆イールドの長期化
2022年3月末には米2年国債の利回りが10年国債の利回りを一時上回る逆イールドが発生した。この逆イールドは2022年7月以降一貫して続き、2023年6月30日には-1.06%という1981年以来42年ぶりの大きさとなった。
これは、FRBの急速な利上げによって短期金利が上昇し、一方で景気減速とそれに伴う将来の利下げを織り込んだ長期金利が上がりにくくなった結果である。2024年9月4日には、米2年債利回りと10年債利回りがともに3.75%となり、2年超に及んだ「逆イールド」がようやく解消された。
高インフレ下の逆イールドの特殊性
現在のような高インフレ期における逆イールドは特に警戒が必要である。例えば、1973年の高インフレ期に発生した逆イールドでは、3か月後、6か月後、1年後の株価もすべてマイナスとなった。FRBがインフレ対策を優先するため、景気が悪化しても金融引き締めを継続する可能性があるからである。
1970年代以降、米国が景気後退に陥る1~2年ほど前に逆イールドが発生する傾向が見られる。しかし、逆イールドが発生しても景気後退が来なかったケースや、株式市場がすぐに下落トレンドにならなかったケースもある。
イールドカーブの形状変化とその意味
スティープ化(Steepening):イールドカーブの傾きが急になり、長短金利差が拡大する現象。金利上昇局面で長期金利の上昇幅が短期金利より大きい「ベア・スティープニング」は景気回復の兆しに見られやすく、金利低下局面で短期金利の低下幅が長期金利より大きい「ブル・スティープニング」は景気後退期に生じやすい。
フラット化(Flattening):イールドカーブの傾きが緩やかになり、長短金利差が縮小する現象。金利上昇局面で長期金利の上昇幅が短期金利より小さい「ベア・フラットニング」は中央銀行の利上げ予想時に、金利低下局面で短期金利の低下幅が長期金利より小さい「ブル・フラットニング」は金融緩和の可能性が高まる景気後退時に起こりやすい。
米国債市場の構造的問題と財政リスク
ベッセント長官の長期債発行に関するコメントは、米国の財政状況と国債市場の深刻な状況を反映している。
膨張する財政赤字
米国の債務は36兆米ドルを超え、将来的にはGDPの134%に達すると見込まれている。2023会計年度の財政赤字は1兆6,951億ドルと、コロナ禍以降で最大となった。
特に懸念されるのは、純利払い費が金利上昇により急増していることである。税収に対する利払い比率は2024年第3四半期に37.8%に急上昇した。パウエルFRB議長も、長期金利上昇の要因として財政の悪化を指摘している。
国債管理政策の失敗
米財務省が2020~2021年の低金利局面で長期債の比率を高めず、逆に短期債の比率を引き上げたことが、金利上昇の影響を強く受ける結果を招いた。これは一部の投資家からは「国債管理政策の失敗」と批判されている。
ベッセント長官が「長期債の増額発行は2021年や2022年にしておくべきだった」と述べたのは、まさにこの失敗を認めた形となる。
ムーディーズによる歴史的な格下げ
2025年5月16日、ムーディーズ・レーティングスは米国債の格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」に引き下げた。格下げの理由は以下の通りである:
- 国家債務の増加
- 長引く財政赤字
- 構造改革の欠如
この格下げは、タームプレミアム(長期債を保有する際に投資家が求める上乗せ金利)の構造的な上昇につながる可能性があると指摘されている。
グローバル投資家の米国債離れ
ジャネット・イエレン氏(元財務長官、元FRB議長)は、現在の不確実性の高い状況下で米国債の利回りが上昇していることについて、外国人投資家が米国の政策の信頼性や世界経済における役割について疑問を抱き始めていることを示唆していると述べている。
通常、不確実性が高まると米国債のような安全資産に資金が流入し、利回りは低下する傾向にあるが、今回は逆の動きが見られた。これは米国債の「安全資産」としての地位が揺らぎ始めていることを示唆している。
FRB議長人事を巡る政治的駆け引き
2025年の米国の金融政策に大きな影響を与える要因として、過去のFRB議長人事の混乱が参考になる。
サマーズ氏とイエレン氏の激しい論争
7月下旬、ワシントンポスト紙のブログ記事が、次期FRB議長の最有力候補がラリー・サマーズ氏であると報じたことで、人選を巡る論争が突如として激化した。元財務長官ではあるものの、金融政策の形成に深く関わった経験がないサマーズ氏が有力候補とされたことは、FRB内部や主要メディア、ニューヨークの金融市場に大きな衝撃を与えた。
この報道後、他メディアや市場関係者からは「反サマーズ、親イエレン」の姿勢が露骨に表れた記事やコメントが大量に流れた。市場とFRBは、サマーズ氏の率直な物言いと過去の舌禍から、彼の議長就任を可能な限り阻止したいと考えていた。
金融危機が変えた人選の慣例
従来は、ホワイトハウスの経済チームがFRB内部や市場との意思疎通を通じて候補者を絞り込み、大統領がその意を汲んで指名するという相互依存関係があった。FRBや市場が支持しない人物を指名すれば、金融政策の決定に混乱が生じ、政権の経済運営に悪影響が及ぶという警戒感があったためである。
しかし、金融危機がこの関係を崩した。オバマ大統領と経済チームは、金融危機からの経済立て直しを主導したサマーズ氏の経済運営能力に絶大な信頼を寄せていた。一方、市場とFRBにとって金融危機克服の立役者はバーナンキ議長であり、金融政策に関わっていないサマーズ氏との距離は近くなかった。
上院では民主党のリベラル派議員が、サマーズ氏が1990年代に推進した金融規制緩和が金融危機を招いたという説得力に欠ける理由を挙げ、イエレン氏を次期議長に推す書簡の取りまとめを進めた。一方で、イエレン氏の組織運営能力を疑う声も出始め、両者の中傷合戦の様相を呈した。
ホワイトハウスの介入と教訓
安定した金融政策運営にはFRB議長に対する金融市場の信認が不可欠であるため、このような中傷合戦はオバマ政権にとってあってはならない事態であった。このため、7月末にホワイトハウスがわずか4日間で議長人事を巡る論争にストップをかけた。
もし候補がサマーズ氏とイエレン氏に絞られる場合でも、イエレン氏にはオバマ大統領との距離、サマーズ氏には金融政策決定への直接経験不足という弱点が残ると指摘された。
トランプ政権の政策がもたらす不確実性
トランプ氏が再び大統領になった場合の政策は、FRBの金融政策にも大きな影響を与えると見られている。
関税政策とインフレ圧力
トランプ政権の輸入関税は、インフレ率を押し上げ、経済活動に悪影響を与える可能性があり、FRBの政策判断に影響を及ぼすと考えられている。イエレン氏は、トランプ政権の関税政策が米国の家計に年間約4,000ドルの負担を強いる可能性があると指摘した。
関税はインフレを押し上げる一方で景気を下振れさせるため、雇用最大化と物価安定を使命とするFRBの政策判断は難しいとされている。トランプ前大統領は、カナダやメキシコからの輸入車に25%の関税を課す可能性を示唆し、中国との貿易戦争を続ける意向を示している。
FRBへの政治的圧力の増大
ドナルド・トランプ前大統領は、FRBに対して露骨に大幅な利下げを迫る政治介入を繰り返していた。彼は、関税による経済悪化や金融市場の動揺リスクを利下げで軽減したいという考えや、景気悪化の責任をFRBの利下げの遅さに転嫁する意図があったとされる。
トランプ前大統領は、FRBのパウエル議長が自身の望む金融緩和を実施しなかったため、再任しないと発言しており、FRBへの政治的圧力を強めている。パウエル議長は、トランプ大統領の利下げ要求が「私たちの仕事には全く影響しない」と述べているが、実際には政治的圧力による利下げと見なされればFRBの信認が落ちることを警戒し、利下げが妨げられていた可能性も指摘されている。
FRBの独立性への懸念
FRBは、大統領に対して政府機関中最も強い独立性を有するとされている。歴代FRB議長は、FRBが政治から独立していることの重要性を強調し、政治的な忠誠心ではなく能力と誠実さに基づいて議長が選ばれることを望む声明を発表している。
イエレン氏は、トランプ大統領が主流とはかけ離れた人物をFRB理事に指名しようとしたことに強い懸念を示しており、そのような人物が議長になった場合、FOMCの予測可能性が失われ、市場の健全なパフォーマンスと安定性が損なわれる可能性があると述べている。
FRBの将来の利下げ見通し – 専門家の予測は分かれる
FRBの利下げのタイミングとペースは、引き続き市場の注目点である。ベッセント長官のFRB批判は、今後の政策運営にも影響を与える可能性がある。
慎重な利下げ姿勢の継続
FRBは2024年9月から利下げに転じたが、米経済が堅調なことを示唆する統計も出る中で、今後どの程度のペースで利下げを継続するのかが焦点となっている。
2025年5月のFOMCでは政策金利が維持され、FRBは当面の様子見姿勢を継続すると示唆した。パウエル議長は、利下げを急ぐ必要はないとの見解を示している。FRBの政策決定はデータ、見通し、リスク動向を総合的に判断して会合ごとに行われる。
専門家による利下げ予測の詳細
複数の見通しが示されているが、2025年中の利下げは1回または2回、もしくはそれ以上という異なる予測が存在する:
- フランクリン・テンプルトン:2024年12月のFOMCで2025年以降の政策金利見通しが引き上げられ、FRBがインフレ動向を注視しながら緩やかに利下げを継続する姿勢を示したと指摘
- 三菱UFJ銀行:2025年、2026年ともに各1回の利下げに止まる可能性を予想
- JTG証券:顕著な経済指標の変化がない限り、利下げタイミングは2025年第4四半期以降にずれ込む可能性があると考えている
FRBが政治的圧力に屈せず、景気悪化の明確な兆候がハードデータで確認されるのを待つ姿勢は、政策対応を遅らせるリスクもある。
過去の金融緩和の行き過ぎへの反省
2020年3月の新型コロナウイルス問題表面化時にFRBが実施した大幅な金融緩和は、トランプ政権による緩和圧力への抵抗の穴埋めのように見え、物価高騰の一因となり、商業用不動産市場の過熱や金融の潜在的な不安定性を高めた可能性が指摘されている。
この過去の経験から、FRBは現在、より慎重な姿勢を取っているとも考えられる。ベッセント長官の「足元ばかりを見ている」という批判は、この慎重姿勢が行き過ぎている可能性を示唆している。
世界経済への波及効果
FRB議長の人選と米国の金融政策は、2025年2月以降の米国の金融政策に大きく影響し、米国経済のみならず、日本や新興国を含む世界経済、さらには国際金融市場や商品市場にも波及する。
グローバル経済の見通し
2025年の世界経済は、米国新政権の政策運営による不透明感を抱えつつも、インフレ鎮静化と金融緩和に支えられ、緩やかな成長ペースを維持すると見られている。その巡航速度は米国の政策動向に左右されるだろう。
特に新興国の金融・商品市場は、これまでの米国の超金融緩和政策によって多額の資金が流入していたため、政策が終了に向かえば資金流出が避けられないという問題も抱えている。
日本経済への影響
日本は賃上げの機運が高まる中、米国通商政策の影響で一時的な景気減速を経るものの、金利のある世界でデフレ完全脱却に向けて前進すると予測されている。人手不足などの構造的供給制約も経済強靭化の鍵となる。
イエレン米財務長官は、日本を含む主要国の為替介入について「根本的な政策変更がなければ、必ずしも機能するとは限らない」との見方を示し、主要国の為替レートは市場で決定されるべきであり、介入は極めて稀に留めるべきだと釘を刺した。
中国の経済政策対応
中国は、より積極的な財政政策と適度に緩和的な金融政策を実施する必要があるとされている:
- 財政赤字対GDP比率の引き上げ
- 超長期特別国債の増発
- 地方専項債の発行増加
- 適時の預金準備率引き下げと利下げ
新興国市場の魅力と課題
唯一インフレ率が市場予想を下回っているのが新興国であるため、特に中南米の現地通貨建て国債が魅力的と見られている。新興国と先進国の成長率格差が拡大すれば、高格付け新興国社債にも恩恵がある可能性がある。
米国の「不確実性の震源地」化
ピクテは、米国のソフトパワーが着実に損なわれ、いずれ米国の資金調達コストの大幅な上昇につながると指摘しており、トランプ政権の政策がこの状況を加速させたと見ている。
米国は世界の安定源から不確実性の震源地へと変貌したため、世界の資金が米国に殺到することは期待できないと述べている。トランプ大統領はすでに投資家に米国債と米ドル以外の選択肢を検討する動機を与えており、「もはや後戻りはできない」としている。
経済政策不確実性指数の上昇
米国の経済政策不確実性指数は、2020年のパンデミック以来の水準まで上昇している。貿易摩擦の激化や緩和が米国に与える影響の全容はまだ不明だが、米国債利回りは、国内・海外両市場での資金調達コストとして重要な指標となる。
米政権が新たな政策発表後の市場の反応、および市場に対する米政権の反応に影響を受ける中で、不確実性が経済成長の足枷となると見られている。
財政構造の問題と社会保障
米国は構造的な財政赤字を抱えており、これが長期金利の高止まりリスクを高めている。
財政赤字削減の困難性
2024年6-7月の米国民世論調査では、ヘルスケア、公的年金、インフラ改善への連邦政府支出拡大の優先度が高く、共和党支持者でも5割前後に達するため、社会保障費用抑制による財政再建は困難と見られている。
そのため、高水準の財政赤字が今後も続く可能性が高いと予測されている。国防や海外援助への支出は抑制される傾向にある。
信用格付け会社の役割と限界
米国債の格下げを決定した信用格付け会社について、その役割と限界を理解することも重要である。
ムーディーズ・レーティングスの評価基準
ムーディーズは、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスクや、デフォルト事由が発生した場合に見込まれる財産的損失を信用リスクと定義している。流動性リスク、市場リスク、価格変動性、その他のリスクについては言及していない。
情報源が信頼できると考えるための必要な措置を講じているが、監査を行う者ではないため、受け取った情報の正確性や有効性について常に独自の検証を行うことはできない。
S&Pグローバル・レーティングの見解
S&Pの格付けは、発行体や特定の債務の将来の信用力に関する現時点の意見であり、債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもない。
業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンス、カウンターパーティの信用力変化など、様々な要因により変動する可能性がある。信頼しうると判断した情報源を利用して格付け分析を行うが、提供された情報について監査や独自の検証は行っておらず、情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではない。
フィッチ・レーティングスの評価方法
フィッチの格付けは、リスクの相対的評価であり、同一カテゴリーの格付けが付与されてもリスクの微妙な差異が十分に反映されない場合もある。特定のデフォルト確率を予測する指標ではない。
事実情報に依拠し、合理的な範囲で調査と独立検証を行うが、情報の正確性、完全性、適時性は保証されない。
債券市場の基礎知識 – 投資家が理解すべき重要概念
ベッセント長官の発言を正しく理解するためには、債券市場の基本的な仕組みを理解することが重要である。
債券価格と利回りの関係
債券は、所有者が借り手に資金を貸し付け、一定の期日に返済されることを確認する証書であり、安定したリターンを求める投資家が好む。債券価格が下落すると利回りは上昇し、価格が上昇すると利回りは下落する。
利回りの上昇は、投資家の債券に対する保有意欲の減退を示唆し、これは発行体の返済能力(国の経済や財政の見通し)やインフレ期待に影響される。
米国債の特殊な地位
米国債は世界最大の経済大国である米国が保証する債券であり、伝統的に安全な資金の避難先と見なされてきた。しかし、近年その相関関係が崩れる局面も見られる。
社債スプレッドへの影響
社債は国債によって「締め出される」可能性がある。国債が市場に大量に供給され、社債購入に見合う利回りの上昇が見られなければ、スプレッド(国債利回りと社債利回りの差)は圧縮され、投資家はリスクに見合う対価が得られないと判断するだろう。
投資家への示唆 – 今後の市場展望
ベッセント財務長官の発言と現在の経済状況を総合すると、投資家は以下の点に注意を払う必要がある。
短期的な見通し
インフレの鈍化が続けば、ベッセント長官が示唆したようにイールドカーブ全体が低下する可能性がある。ただし、財政赤字の拡大や格下げリスクが、長期金利の下げ幅を限定的にする可能性もある。
中長期的なリスク要因
- 財政問題の深刻化による金利上昇圧力
- 政治的不確実性の高まり
- 予想外のインフレ再燃
- FRBの政策運営の遅れ
- 国際的な米ドル・米国債離れ
ソフトランディングへの期待と懸念
イエレン米財務長官は、米国経済の「ソフトランディング」達成を主張しつつも、景気後退リスクが「完全には排除されていない」と述べている。一部の専門家は、利上げ局面入りで堅調な展開が続くと見ており、景気後退は深刻ではなくソフトランディングに向かうと予測している。
まとめ – 転換期にある米国金融システム
ベッセント財務長官の「FRBは凍り付いている」という衝撃的な発言は、米国の金融システムが直面する深刻な課題を浮き彫りにした。2022年の急激な金融引き締めの後遺症、長期化した逆イールド、膨張する財政赤字、そして前例のない米国債の格下げなど、多くの構造的問題が山積している。
FRBは過去の失敗に囚われ、前を向いていないという長官の批判は、金融政策の機動性が失われていることへの警鐘である。同時に、長期債発行のタイミングを逸した国債管理政策の失敗も認めざるを得ない状況にある。
投資家やビジネスパーソンにとって、この転換期における米国経済の動向は、単なる一国の問題ではない。世界の基軸通貨を持つ米国の金融政策は、日本を含む世界経済に大きな影響を与える。ベッセント長官の率直な発言は、我々に米国経済の現実を直視し、新たな時代に備えることの重要性を示している。
今後は、FRBの政策転換のタイミング、財政問題の解決への道筋、そして政治的不確実性の行方に注目しながら、柔軟かつ慎重な投資戦略を構築することが求められるだろう。米国が「不確実性の震源地」となりつつある今、グローバルな視点での分散投資の重要性はさらに高まっている。
関連記事:
参照サイト:S&Pグローバル・レーティング | フィッチ・レーティングス | 長期イールドカーブ分析 | 米国債 – Wikipedia | 連邦準備制度 – Wikipedia
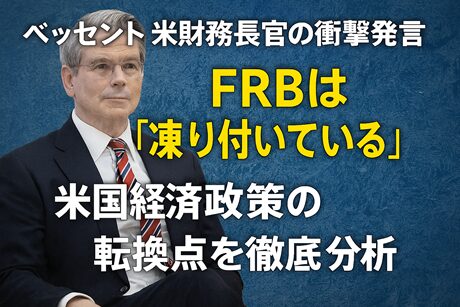


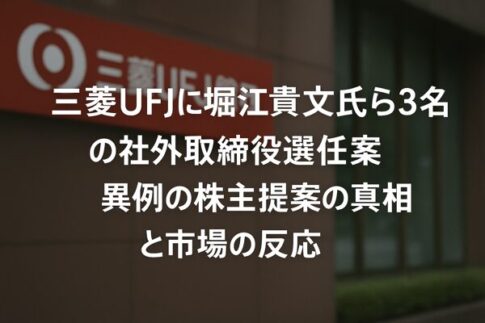



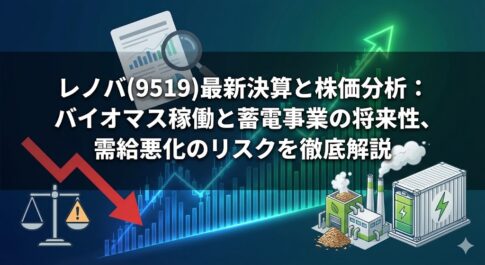
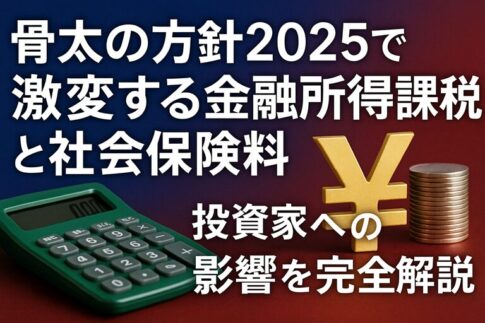



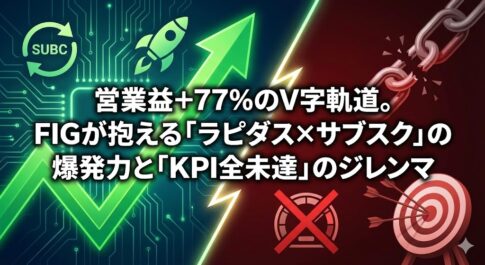






コメントを残す