目次
期日前投票の「不正疑惑」は本当か?SNSで広がる懸念と選挙制度の実態を徹底検証
2024年の参議院選挙において、X(旧Twitter)上で「期日前投票は不正し放題」という投稿が拡散され、選挙制度への不信感が広がっています。特に「本人確認なしで投票できる」という指摘が注目を集め、多くの有権者が選挙の公正性に疑問を抱いています。
しかし、これらの懸念は本当に根拠があるのでしょうか。今回は、SNS上で飛び交う様々な意見から、選挙管理の専門家の見解、そして実際に起きた不適正処理の事例まで、期日前投票をめぐる問題を多角的に検証していきます。
期日前投票への関心の高まりと有権者の声
まず注目すべきは、今回の参議院選挙における期日前投票の利用状況です。X上では、期日前投票に関する多数のポストが投稿されており、そこから国民の選挙に対する様々な意見や見解が読み取れます。
混雑する投票所と高まる関心
期日前投票所の混雑状況に関するコメントが多数寄せられています。「期日前投票めっちゃ並びますやん」「アルプラザの期日前投票に行ったけど約40分待ちやった」といった投稿が複数見られ、「結構な人が期日前に来ててビックリよー」「例年より投票する人が多かったことに驚いた」という声も上がっています。
ただし、混雑状況は時間帯や場所によって異なるようです。「衆議院選と違って昼過ぎに行ったから並ぶ事もなく一瞬で終わった」という報告もあり、「平日の期日前投票しか行ったことないから関心度が高いのかいつも土日はこんなに待つのかどっちねんろ??」と、混雑が全体的な関心の高さを示すものなのか、単に週末の傾向なのか疑問を呈する声もあります。
また、「高津区役所は期日前投票の人が結構いるわ 連休の中日にいくのダルいしねぇ それが狙いっぽいけど」といった、やや皮肉めいた見方も見られました。
期日前投票を利用する理由
多くのユーザーが期日前投票を利用する理由として、以下のような事情を挙げています:
- 「投票先決まっているかつ選挙当日は旅行中なので早いところ期日前投票に行かないと」(旅行予定)
- 「丸亀のフレッシュオールスターで現地行くために期日前投票今日行こ」(イベント参加)
- 「来週は忙しいし期日前投票行ってくるかー」(仕事の都合)
- 「来週実家帰るから期日前投票行ってきた✌️」(帰省予定)
- 「マイナンバー更新のついでに期日前投票行ったけど」(他の用事と合わせて)
「ひっさびさに選挙行ったわー、期日前投票ありがたい」という声からは、投票に行く機会が少ない層にとっても、期日前投票が重要な投票機会を提供していることがわかります。
有権者の政治意識と投票動機
現政権・政治状況への不満
X上の投稿からは、現在の政治状況に対する強い不満が読み取れます。「みんな今の🇯🇵にウンザリよね、、、次のステップ進まないといけないのよー」という声や、「今回は本気でみんな自民党に愛想尽かした人増えた気がするw w 嘘つきはオオカミに食べられるっておとーが言ってた!」といった、与党への失望を示す投稿が見られます。
一方で、「どこの党も一緒だな、実行出来ないこと平気言うし まあ行かないとそれはそれでな」と、政党全般に対する諦めや不信感を抱きつつも、投票の必要性を感じている人もいます。
具体的な投票動機
投票の動機については、個人の価値観が強く反映されています。特に印象的なのは、「教育の質を高めるために、先ずは先生方の待遇が最大限に改善されるよう、祈りを込めて投票しました。私は将来への投資、大好きです!」という投稿です。教育問題を「将来への投資」と捉え、明確な意図を持って投票に臨む姿勢が示されています。
また、「誰に投票するかは決まっていたので、迷うことはなかった」と、事前に明確な意思を持って投票する人もいれば、「比例は北村弁護士一択なんだけど埼玉の方は誰がマシなのがちで」のように、比例代表では明確な選択肢があるものの、選挙区では迷っている様子も見られます。
政党支持に関しては、「やっぱり国民民主党が自分の考え方にはピッタリ合うな〜☺️」という声や、自民党員でありながら比例代表で特定の候補者名を記入し、選挙区で別の候補者を応援したという詳細な投票行動を記す投稿もありました。
SNSで広がる「期日前投票の不正疑惑」
期日前投票への関心が高まる一方で、その制度に対する不信感も広がっています。X上では「期日前投票は不正し放題」という意見が拡散し、様々な懸念が表明されています。
本人確認の甘さへの懸念
最も多く指摘されているのが、本人確認の不備です。あるユーザーは次のように投稿しています:
「期日前投票って投票用紙が無くても本人確認無しで投票できるから他人の名前や住所を使って複数回の投票が可能となってしまう」
この問題について、「この問題は以前から散々指摘されてきたのにワザとなのか、一向に是正しないのは何故でしょうか」という疑問も呈されています。
JBpressの記事では、大阪市の主婦が実際に期日前投票を行った際の体験が紹介されています。「身分証明書を提示しないでも大丈夫だったの?」「こんなやり方ではなりすましの投票ができるんじゃないかと疑問に思った」と語っており、住所・氏名・生年月日を伝え、選挙人名簿と合致し、年齢に近い風貌であれば「なりすまし」投票が可能であるという認識が示されています。
また、「手ぶらで期日前投票推してるの自民党だけじゃない?」という、特定の政党の選挙戦略に対する疑念を示す投稿も見られました。
市民による監視の呼びかけ
こうした懸念から、市民による監視を呼びかける声も上がっています:
「不正の抑止力だけでも良い。期日前投票は、その場所が役所になるため、場所の範囲はそこまでめちゃ多くない。どなたか平日時間のある方、役所の期日前投票所に足をお運び頂けると助かります。何も無かったら無いで、それが一番いいんです。」
元候補者による衝撃的な証言
さらに深刻な疑惑を提起しているのが、2016年の参議院選挙に立候補した経験を持つ人物のブログです。この元候補者は、自身の経験から選挙制度に対する強い疑念を表明しています。
練馬区の開票所での異常:
- 開票前から候補者ごとの「票を入れる籠」の数がすでに決まっており、誰が何票取るかが”予定されている”かのような雰囲気を感じた
- 別の開票所では「投票用紙が紛失した」とアナウンスされた後、「見つかった」として持ち込まれた大量の投票用紙の枠線の色が正規の用紙と違っていた
- 自身の支持者が投票したと明言しているにも関わらず、特定の市(我孫子市)で得票が0票であったことを「どう解釈すれば良いのか?」と問いかけている
構造的な問題の指摘:
- 元創価学会員で公明党の開票立会人を務めた人物も、「現場で不正と思しき光景を目にした」と証言した
- 期日前投票所の多くで監視カメラがなく、夜間の保管体制が不十分である可能性
- 投票箱の運搬を民間のタクシー業者が担っており、その協会が自民党を支持しているという事実
- 開票作業に使われる機械を製造する「ムサシ」の役員が、安倍晋三元首相や麻生太郎元財務相の親戚であるという話(公的には未確認)
この元候補者は、「市民が疑問を持つに足る”構造”があることは否定できません」と結論付けています。
選挙管理当局と専門家の見解
これらの疑惑や懸念に対し、選挙管理を行う当局や専門家はどのように説明しているのでしょうか。
日本ファクトチェックセンターの検証
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、「期日前投票は不正し放題」「鉛筆だと書き換えられる」といった投稿について、誤情報であると指摘しています。
期日前投票の管理体制について:
- 期日前投票の箱は鍵がかけられ厳重に封印されている
- 開封は開票時のみで、開票は「衆人環視のもとで実施される」ため不正は困難
- 投票箱が鍵をかけて封印され、多数の監視の目があるため、消しゴムで消して書き直すことは不可能に近い
鉛筆使用の理由:
投票所で鉛筆が用いられるのは、投票用紙が特殊な紙でできており、折りたたまれても開きやすく、開票時の手作業の手間を省けるためだとされています。
選挙ドットコムの専門家による説明
選挙ドットコムの専門家は、不正選挙陰謀論を以下の理由で否定しています:
- 選挙事務に当たる市町村の公務員は法律によって厳しく律されており、選挙の公正さが担保されている
- 投票用紙は切手や株券と同じ「証券印刷部門」で厳重に作成され、選挙ごとに少しずつ違っているため、過去の選挙で余った白票や偽造用紙を混入させてもすぐに発覚する
- 投票箱の管理は投票管理者など複数の職員が複数の鍵で厳重に管理しているため、投票用紙を抜き出して書き換えることは「絶対に無理」
- 多数の職員が関わる選挙において、職員を買収して不正を働かせることは不可能
- 各候補者の陣営から「開票立会人」が監視しているため、意図的な当選者変更は不可能
本人確認を義務化しない理由
なぜ厳格な本人確認を行わないのかについて、大阪市は以下の理由を挙げています:
- 手続きの複雑化による投票所の混雑を避けるため
- 待ち時間の増加を防ぐため
- 本人確認書類を持たない人の投票権を保障するため
ただし、完全に無防備というわけではありません。投票案内状の持参者には誕生日を、不持参者には住所・氏名・生年月日を確認するなど、不正防止のための本人確認は実施しており、不審な点があれば本人確認書類の提示を求めるとしています。
衆議院に対する答弁書では、投票所で顔写真付き身分証明書の提示を義務付けることは検討していないとされています。
実際に起きた不適正処理事例 – 甲賀市の教訓
意図的な不正ではないものの、選挙事務において深刻な不適正処理が発生した事例も存在します。その代表例が、平成30年(2018年)に甲賀市で発生した事案です。
事案の概要
甲賀市では、開票事務に携わる職員が、投票者数と開票数の齟齬を隠蔽するため、未使用の白票を不正に使用して集計し、その後未集計の投票用紙を処分したことが判明しました。これは公職選挙法上の「投票増減罪」に当たる可能性があり、市行政への信頼を大きく揺るがす重大な事案とされています。
不適正処理の要因分析
検証報告書では、この不適正処理の原因を心理的要因、環境的要因、物理的要因の三つの側面から詳細に分析しています。
心理的要因:
- 「選挙事務は選挙管理委員会が行うもので、私たちは事務を頼まれた立場である」という意識が強く、市職員としての本務であるという自覚が不十分
- 「早く終わらせて通常の業務に戻りたい」「翌日に仕事を残したくない」「ミスは絶対に許されない」という重圧から、コンプライアンス意識が欠如
- 不測の事態発生時に、適切な判断を下し、相談できる組織環境や風土が不足
環境的要因:
- 衆議院議員総選挙と市議会議員一般選挙の同日執行により、事務が輻輳し、一部の職員に負担が偏った
- 開票事務における全体的指揮や個別担当事務の指揮を執るべき責任者の立場が不明確
- 開票事務従事者は白色の腕章を着用していたが、投票箱送致職員や開票立会人などは明確な表示がなく、入場許可者の区別やチェック体制が不十分
- 開票事務マニュアルが経験のない職員への配慮に欠け、開票録の記載例がないなどの不備
- 開票状況の経過や実態を示す詳細な記録(動画など)がなく、事務の実態を検証するためのデータが不足
- 投票者数と開票数の齟齬発生ケースなど、不測の事態へのシミュレーションや対応ルールが不足
- 選挙開票当日が台風襲来と重なり、緊急避難情報が発表されたことで、開票事務従事者の意識が散漫になった
物理的要因:
- 投票所で残った白紙の投票用紙や選管が予備的に保管していた用紙の管理が不明確で、誰でも持ち出し可能な状態
- 投票箱1つの所在が不明となり開函できなかった。どの投票箱をどこに置くか、誰が担当するか、各段階での複数人によるチェック体制が未確立
- 審査係の机上の計数機で不適正に白票が集計された。予備の計数機が誰でも持ち出せる状態だった
再発防止策の実施
甲賀市では、上記の要因を踏まえ、包括的な再発防止策を実施しました。
1. 職員の意識改革と法令遵守の徹底:
- 全ての市職員に対し、公職選挙法を含むコンプライアンスに関する研修会を定期的かつ複数回実施
- 地方公務員法に定められた「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する」という意識の徹底
- 上司は組織防衛意識よりも公共の利益を優先し、部下は違法な命令には従わず、違法性を進言できる風土を構築
- 職員一人ひとりが「選挙事務は自らの仕事である」と考え、その趣旨を理解し、お互いに協力し意見を出し合える組織環境を醸成
- ミスをミスとして報告し、組織として対応を検討し、原因を追究して再発防止策を講じる風土の実現
- 「不正処理は絶対に許さない」という正義感を持ちつつ、ミスは避けられないことを前提に、ミス発生時でも法令を遵守することを自覚
2. 体制と環境の改善:
- 開票事務と投票事務の兼務を原則廃止し、ミスの発生リスクを軽減
- 選挙期間中、一部の職員に事務が偏らないよう、仕事の割振りを適切に実施
- 指揮を執る従事者を専任とし、明確な指示体制を構築
- 開票事務従事者全員が現在の進捗状況を理解できるよう、都度、場内アナウンスを実施
- 係ごとに色分けしたベストの着用、事務主任や機器保守業者の腕章着用など、役割と作業状況を明確化
- 投票箱の開錠前に扉を閉鎖し、出入口に担当者を配置して事務従事者以外の出入りを厳格に管理
- 職員研修用として開票所内にビデオカメラを複数箇所に設置し、一連の開票作業を動画として記録・保存
3. 書類と用具の管理改善:
- 各投票所から送致された残余の白紙投票用紙や予備の投票用紙は、枚数確認後に開票管理者が封印し、選挙終了時まで開票管理者と開票立会人の監視できる場所で保管
- 全ての投票箱を開票所内に搬入し、担当者が所定の開票台で開披。投票箱の確認係を設け、投票用紙が残っていないか複数人で確認
- 予備の計数機などの機器は、庶務係の管理できる場所に置き、持ち出す際には目的と使用場所を報告
選挙事務の厳格性と誤解を招く要因
選挙管理委員会は、有権者に誤解を与えないよう様々な努力をしています。過去には、開票所で職員がポケットに手を入れたり、ポーチを持ち込んだり、影に隠れて何かをしていたといった外形的な状況が「不正開票だ」「投票用紙を隠したのではないか」とテレビ局で報じられた事例があります。
もちろん不正はなかったとされていますが、こうした誤解を招く動きに注意を促す「基本的留意事項」をまとめ、職員に徹底しています。一部の市では、開票事務にビデオカメラを導入しており、これは職員の緊張感を高めるとともに、後の検証に役立てることを目的としています。
選挙管理アドバイザーの小島氏は、選挙における不正行為を防ぐ上で最も重要なのは、職員の選挙に対する意識に帰着すると述べています。普段他の業務をしている職員にとって、選挙は「選挙の時だけの頼まれ仕事」という意識になりがちで、これがミスを犯したり、数が合わない場合に白票を増やそうとする可能性につながることがあります。
開票は、一つ一つ慎重に手順を踏んで行えば、正確にある程度の時間で終わるものであり、「作業ではなく仕事」をするという意識付けが重要だとされています。
期日前投票制度の課題と改善提案
宣誓書の問題
期日前投票の際に提出が求められる宣誓書について、全国の多くの自治体から廃止または簡素化を求める提案が寄せられています。今金町、別海町、花巻市、多賀城市、白鷹町、安中市、練馬区、相模原市、魚沼市、桑名市、枚方市、八尾市、熊本市、延岡市など、全国町村会もこの提案に賛同しています。
提案の理由:
- 宣誓書が高齢者や障害者にとって負担である
- 簡素化により短時間で投票が可能になり、期日前投票所の混雑緩和につながる
- 投票率向上、感染症予防の効果が期待できる
しかし、総務省の回答では、期日前投票はあくまで当日投票の例外であり、投票が困難である一定の事由を本人申立てにより確認する必要があるため、事由の選択廃止や氏名・日付のみの記載への簡素化は適当ではないとされています。宣誓は書面で行う必要があり、口頭による申立ては認められていません。
早稲田大学の視点からは、現行の期日前投票制度は、かつての身体的制約や貧困による救済目的の「不在者投票」を超え、「投票率を上げる」という一般的な効果を目的に導入されたと指摘されています。旅行やレジャーといった理由でも投票が認められている点が挙げられ、高い投票率が選挙の正当性を高めるという民主主義の理念に基づいて推進されていると説明されています。
高齢者の投票環境向上と郵便等投票
本研究会では、要介護3以上の高齢者を郵便等投票の対象とすることに概ね意見が一致しています。これは、投票所まで行くことが困難な要介護者を救済するためです。
より厳格に対象範囲を考える場合、寝たきり度や要介護認定調査の歩行関連項目の評価といった付加条件を考慮することも考えられます。しかし、これらの付加条件は、現状では本人に通知されるものではなく、追加の証明を求める必要が生じるため、選挙人や実務担当者(介護福祉部局、選挙管理委員会)にとって負担が増すという課題があります。
郵便等投票の公正確保策:
- 罰則を含めた制度の周知徹底
- 投票用紙を送付する際に、有権者本人が自ら投票用紙に記載する必要があることや、不正な投票には罰則があることを明確に案内
- 第三者の立会人配置や、投票記載を自ら行った旨の誓約書の同封も検討されたが、実務上の困難から見送り
指定施設における不在者投票
病院などの施設長が選挙人に代わって投票を請求する場合、施設長が選挙人が一人で投票所に行けるか困難かを判断します。選挙人が歩行可能で、施設が投票区内にある場合、投票日当日に仕事や用事がない限り、施設での不在者投票はできません。
「期日前投票宣誓書 兼 不在者投票請求書・宣誓書」では、有権者が期日前投票または不在者投票を行う理由として6つのうち1つに丸を付ける形式となっています。
選挙制度への信頼回復に向けた提言
早稲田大学・河野勝教授の提言
選挙における「なりすまし」や「二重投票」の問題について、早稲田大学の河野勝教授は重要な提言を行っています。河野教授は、これらの不正の悪影響と、それらを防止するための規制強化がもたらす投票率低下の悪影響を比較衡量する必要があるとし、現状では不正がどの程度頻繁に起こっているか実証的な根拠がないと述べています。
そのため、まず実際にどのくらいの割合で「なりすまし」や「二重投票」が起こっているのかをきちんと調査し把握することが重要だと提言しています。全ての投票者に本人確認書類を求めるのが非現実的であれば、「抜き打ちのサンプル調査」を実施し、その結果次第で規制強化の要否を判断すべきだと提案しています。また、こうした抜き打ち調査の事前アナウンスは、不正の抑止力としても機能すると考えています。
選挙制度への批判と改善要望
X上では、選挙制度の様々な問題点が指摘されています:
- 「立憲と国民の略称がどちらも民主党問題は解決されてない」 – 有権者の混乱を招く可能性のある政党名の略称問題
- 「期日前投票はやいところはいいなぁ なんで投票日3日前からなんだよ」 – 期日前投票期間のさらなる拡大を望む声
- 「報道は主要な党しか出さないから5、6人くらいだと思っていたのに」 – メディアの報道姿勢に対する不満
また、特定の政党(参政党)について、「反農薬や反ワクチンなど非科学的な要素が悪魔合体している所」が特に問題であるという批判的な意見も存在します。一部の候補者が「直近のコメ騒動のせいで農産業の類を対策しますって書いててウケる(ウケない…)」と、政策の内容に対する皮肉めいた見方も見られます。
メディアへの不信感
投票後のNHKのアンケートに対して「絶対答えたくない ジャニーズのことは絶対忘れない」と回答を拒否する様子が示されており、特定のメディアに対する不信感が選挙とは異なる社会問題と結びついて表れています。
国外の事例から学ぶ教訓
選挙の公正性に関する問題は、日本だけでなく世界各国で議論されています。
アメリカの事例:
2016年のアメリカ大統領選において、ロシア政府によるサイバー攻撃や電子メールの漏洩が確認されています。これは、選挙への外部からの干渉という新たな脅威を示しています。
韓国の事例:
韓国では、過去の選挙で不正があったとする「不正選挙陰謀論」が保守派の一部で根強くはびこっており、偽造投票用紙の混入や選挙管理委員会へのハッキング疑惑が主張されることもありました。しかし、事実を裏付ける証拠は明らかにされていません。
投票者の層と期日前投票の意義
X上のある投稿では、投票者の層について興味深い指摘がなされています:
「真面目に投票行くのが、ヒマで裕福なお年寄りや、生活に困ってないそこそこ金持ちの家庭だからね 期日前投票は入れたくないが、投票日すら仕事が忙しくて行けないっていう人達にこそ行って欲しいのに」
この投稿は、期日前投票の本来の目的(忙しい人の投票促進)への期待を示すとともに、有権者の層に対する偏見も含んでいます。しかし、実際の期日前投票の利用者を見ると、様々な背景を持つ人々が活用していることがわかります。
まとめ:選挙制度の信頼性向上に向けて
期日前投票をめぐる議論は、単なる制度論にとどまらず、日本の民主主義のあり方そのものを問いかけています。X上での活発な議論は、国民が選挙制度に高い関心を持ち、その公正性を重視していることの表れです。
確かに、現行制度には改善の余地があります。本人確認の厳格化、投票箱の管理強化、開票作業の透明性向上など、検討すべき課題は多岐にわたります。しかし同時に、過度な規制強化が投票率の低下を招く可能性も考慮しなければなりません。
甲賀市の事例が示すように、制度の問題だけでなく、選挙事務に携わる職員の意識改革も重要です。「選挙事務は自らの仕事である」という自覚を持ち、ミスを隠蔽するのではなく、透明性を重視する組織文化への転換が求められています。
また、河野教授が提言するように、まずは実態調査を行い、エビデンスに基づいた議論を進めることが重要です。根拠のない陰謀論に惑わされることなく、建設的な改善策を検討していく必要があります。
期日前投票は、多忙な現代社会において重要な投票機会を提供する制度です。「教育の質を高めるために、先生方の待遇改善のために投票した」という声に代表されるように、明確な意思を持って投票に臨む有権者の期待に応えるためにも、より信頼性の高い選挙制度の構築が求められています。
私たち一人一人が選挙制度に関心を持ち、その改善に向けて声を上げることこそが、民主主義を守り、発展させる第一歩となるのではないでしょうか。
参照サイト: 総務省 | 選挙管理研究会報告書 | 甲賀市検証報告書 | 日本ファクトチェックセンター
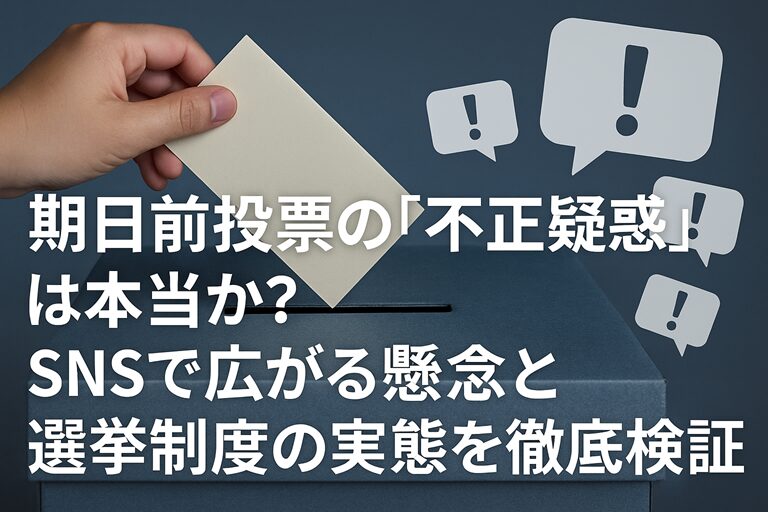

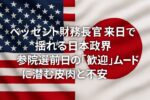
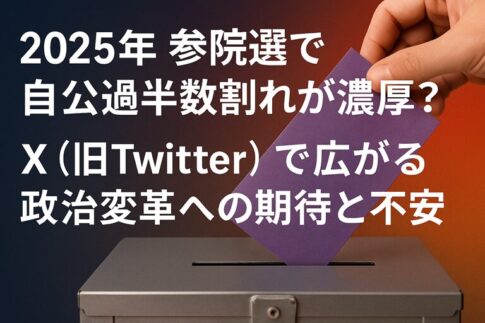




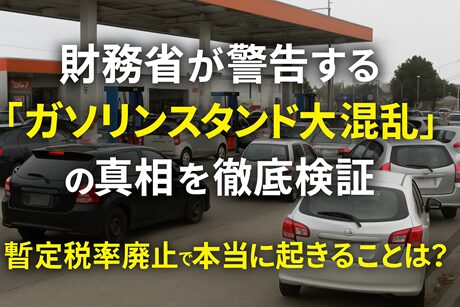

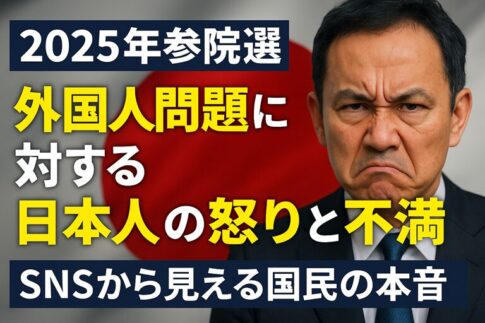

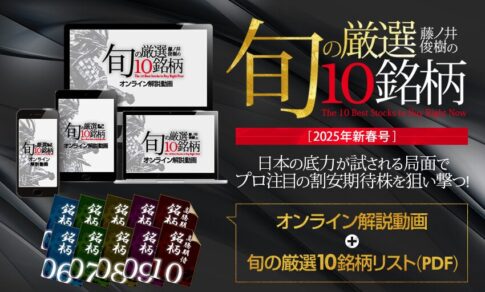








コメントを残す