目次
- 1 2025年参議院選挙で争点化する外国人政策 – 各党の公約と議論を徹底分析
2025年参議院選挙で争点化する外国人政策 – 各党の公約と議論を徹底分析
1. 難民保護に関する政策
難民保護のあり方は、各政党で明確な違いが見られます。
移民や難民を排除するのではなく、多文化共生社会を目指すことを政策の柱としています。
難民保護に関する具体的な政策は、公約に「該当する政策なし」と明記されています。
入管庁から独立した難民認定機関の設立について
設立に肯定的/必要と考える政党
立憲民主党は、国際法違反との批判を受ける現行の難民認定・収容送還制度を抜本的に見直し、政府から独立した第三者機関である「難民等保護委員会」の創設を柱とする「難民等保護法・入管法等改正法」の制定を目指しています。
日本共産党は、現行の難民認定や難民審査参与員制度が入管庁の裁量に委ねられ、公平性・中立性に欠ける運用がされてきたと批判し、出入国管理と難民保護を行う主体を分離することが必須だと考えています。
れいわ新選組は、国際的な人権ルールに基づいて、保護すべき難民申請者や補完的保護対象者を適切に保護できる新たな難民認定・保護制度の確立を目指すとしています。
社民党も、独立機関の設立が必要であると考えています。
設立に消極的/否定的態度を示す政党
公明党と日本維新の会は、難民認定機関の独立設立に否定的な態度を示しています。日本維新の会は、現行の入管庁で難民認定は十分可能であると主張しています。
国民民主党は「その他」と回答し、慎重な姿勢を見せています。外国人の受け入れは、日本語教育支援などを国が主体的に行うとともに、日本国民との協働・共生が地域社会で推進されることが大前提であり、国としての在住外国人政策の全体的な方向性や計画を明確にした上で、現実的な検討が行われるべきだとしています。
参政党は、入管庁から切り離された独立機関による難民認定や不服申立ての意見には、公正性確保の点で理解できる部分があるとしつつ、重要なのは機関の内外ではなく、判断の透明性と制度的責任の明確化だと述べています。
2. 外国人の権利保障と共生に関する政策
外国人の権利保障や共生社会の実現に向けた政策も、各党の立ち位置が異なります。
罰則規定のある差別禁止法をつくり、移民、難民を排除しない多文化共生社会を目指すことを公約としています。
外国人の権利保障や共生に関する政策については、公約に「該当する政策なし」と明記されています。
外国人人権基本法の制定
積極的な姿勢を示す政党
立憲民主党は、国際人権条約に基づき、インターネット上の誹謗中傷を含むあらゆる差別の解消を目指す「包括的差別禁止法」を制定し、新たな人権救済機関の設置と個人通報制度の導入を推進するとともに、人権の尊重を基本とした「多文化共生社会基本法」の制定も目指しています。また、罰則規定のある差別禁止法や「外国人労働者安心就労法」の制定、在留資格全般の見直しも推進するとしています。
日本共産党は、外国人を日本社会の一員として、対等な社会参加で共生社会を築く理念を掲げることは、多文化共生の取り組みを進める上で重要だと考えています。罰則規定のある差別禁止法の制定を求めています。
れいわ新選組は、全ての人に対して基本的人権が保障されるべきであり、条約に基づき、外国人の包括的な権利を規定する法律を制定すべきだと主張しています。外国人労働者への賃金差別の規制や、在留外国人の法制度を「管理」から「権利の保護」へと改定するとしています。
社民党は、国際人権条約に基づき「外国人人権基本法」を制定すべきという立場を支持しており、現在の法制度では外国人の権利保障が不十分であるため、この法整備が必要不可欠だと考えています。
消極的な態度を示す政党
公明党は、基本法の制定については既存法の制度との整合性などを踏まえた慎重な検討を要するものの、外国人の人権を尊重し共生社会の実現を目指すためには、今後の社会情勢や課題を踏まえて制度や政策のあり方を検討していくことは重要だと考えています。
日本維新の会は、日本は国際人権条約に加盟しているので、十分に外国人の権利は守られているとして、新たな基本法の制定には消極的です。
参政党は、包括的立法は日本国民の権利や社会制度との間で摩擦や緊張関係を生じさせる懸念があるため、拙速な法制化に慎重であるべきだと主張しています。
3. 在留管理の強化と送還促進に関する政策
在留外国人の管理を強化する政策については、与党および一部の野党が言及しています。
難民保護・外国人権利保障・共生に関する政策は明記なし。在留管理の強化と送還促進に重点を置いており、近年指摘される外国人による運転免許切替や不動産所有などの問題に対し、法令に基づき厳格かつ毅然と対応し、「違法外国人ゼロ」を目指す取り組みを加速するとしています。
石破総理は、外国人が増える中でトラブルも起きていることを認め、「ルールをきちんと守ろうよ」と発言しています。また、外国人の犯罪や制度の不適切利用に対する国民の不安や不公平感を認識し、政府一体で対処する「外国人政策の司令塔組織」の設置を打ち出しています。
多文化共生社会を目指し、移民や難民を排除しないとしています。外国人による社会保険料の未納情報を在留審査に反映させるなど、在留管理の高度化を掲げています。
難民保護に関する政策は明記なし。外国人比率の上昇抑制や受け入れ総量規制を公約に明記しています。また、帰化審査の厳格化と取り消し制度の創設も政策に盛り込んでいます。
「外国人総合政策庁」の新設と、外国人政策に関する理念法の整備により、関係各省庁と連携しながら、受け入れ基準や制度の運用を一元的に管理する方針です。単に労働力不足を補う目的での無制限な外国人受け入れに反対し、国益を重視し、持続可能で安全な社会を築くための管理型外国人政策への転換を提唱しています。
神谷代表は、今回の選挙のキャッチコピーを「日本人ファースト」とし、日本人の暮らしを守ることを強調しています。
難民保護に関する政策は明記なし。「野放図な移民政策を是正する」と表明しています。入管難民法の改正と運用の厳格化、外国人を別立てにするための健康保険法や年金法の改正を掲げています。
百田代表は、金を持つ外国人が生活の場を投機物件のように買いまくり、値上がりしていることに対し、政府が全く手立てを打っていないと批判しています。
4. 外国人労働者の受け入れに関する政策
人口減少が続く中で、外国人労働者の受け入れを拡大するか制限するかは、参院選の重要な争点となっています。
人口減少を踏まえた外国人労働者の受け入れについては「どちらかと言えばそう思わない」としつつも、経済社会の活性化のためには一定範囲での受け入れが不可欠であると認識しています。外国人労働者が日本社会で長く活躍できるよう、日本語教育の充実や社会生活ルールの丁寧な教育といった行政支援が課題であるとし、育成就労制度の円滑な運用開始に向けて政府への提言を行っています。
外国人労働者の受け入れは積極的に進めるべきとの姿勢で、「外国人の方に入っていただき、仕事をしてもらわないと日本は回らない」と強調しています。国内で約230万人以上の外国人労働者が経済活動を担い、約300万人以上の外国籍の人が生活者として在留している現状を踏まえ、活力ある日本社会・経済を維持・増進していくためには、今後も多くの外国人労働者が夢と希望を持って来日し、安心して働いて生活できる環境の整備が必要不可欠だと考えています。
外国人労働者の受け入れについては、理念も制度もないまま経済合理性のみで進めると社会の不安定化や国民負担の増大、国内労働者の賃金押し下げを招く懸念があるとし、消極的な態度を示しています。「外国人総合政策庁」の新設と理念法の整備により、管理型の外国人政策への転換を主張しています。高度な技術や専門知識を持つ人材を優先し、非熟練労働者の受け入れには制限を設けるとしています。
外国人労働者の受け入れは、制限そのものに反対し、受け入れた外国人の人権・労働条件の保障を強化することを優先すべきであるとしています。外国人労働者を「安価で使い捨て可能な労働力」として扱う政策に反対し、日本人労働者と同等の賃金・労働条件・社会保障へのアクセスを保障されるべきだと主張しています。
田村委員長は、社会の不満のはけ口を外国人に向けることは間違いであり、いずれ国民にも向かうと警鐘を鳴らしています。
外国人労働者の受け入れについては「どちらかと言えばそう思わない」としており、外国人受け入れは日本語教育支援や日本国民との協働・共生が前提であり、国としての明確な政策や計画が必要であるとしています。
当初は「外国人に対する過度な優遇を見直す」という表現を公約に盛り込んでいましたが、「外国人に対して適用される諸制度の運用の適正化を行う」と修正しました。玉木代表はこの修正について「排外主義的だという批判をもらった。誤解を解く意味で修正した」と説明しています。
「移民政策に反対する」としています。山本代表は、低賃金外国人労働者の流入が日本人労働者の置き換えにつながっていると批判し、「国民を見ろ」と訴えています。「移民、難民を排除するのではなく、多文化共生の社会をめざします」としつつも、深刻な人口減少を理由とした外国人労働者の受け入れ拡大論には賛同せず、これは低賃金労働力の導入が目的であり、国内労働者の賃金下押し圧力として機能していると批判しています。
外国人および外国人労働者の受け入れ制限そのものに反対し、むしろ受け入れた外国人の人権・労働条件の保障を強化することを優先すべきであるとしています。「排除」より「共生」、「搾取」より「平等な労働条件の保障」が基本方針であり、外国人労働者を単に「安価で使い捨て可能な労働力」として扱う政策には反対です。
人口減少対策として外国人労働者の受け入れを拡大することには消極的で、現状のように理念も制度もないまま経済合理性のみで進めれば、社会の不安定化や国民負担の増大を招き、国益を損なうおそれがあると指摘しています。低賃金労働力の流入は、国内労働者の賃金を押し下げる懸念も大きく、劣悪な労働環境で働かせる実態は人道上の問題でもあり、日本の国際的評価にも影響すると考えています。
5. 永住許可取消制度(2027年4月施行予定)
昨年の入管法改定で導入された永住許可取消制度に対する各党の意見です。
立憲民主党:永住許可取消制度については、不必要で差別的な施策であり、削除が必要であると表明しています。
日本共産党:永住許可取消制度は外国人差別であり削除が必要であると強く反対しています。
れいわ新選組:改正永住許可取消制度は、すでに国籍を問わず刑事罰や税金滞納の差し押さえ手続きがあるにもかかわらず、永住者に対し不平等なペナルティを課すものであり、不必要で差別的な施策だと考えています。
社会民主党:永住許可取消制度には強く反対しており、永住者の人権に重大な影響を及ぼすとし、「事実上の国外退去処分」に等しいと考えています。
日本維新の会:永住許可は一度得れば自動的に無期限で保持できるものではなく、要件を満たさなくなった場合の取り消しは当然であるとし、永住許可取消制度の必要性を肯定しています。
参政党:永住許可は、法務大臣が「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その永住が日本国の利益に合すると認められること」などを審査し、要件を満たすと判断した場合に付与される地位です。したがって、これらの要件を満たさなくなった場合に許可を取り消すことは、制度の趣旨に照らして当然であると考えています。
6. すべての子どもの学びの権利保障
在留資格に関わらず、すべての子どもが教育を受ける権利を保障することに対する各党のスタンスです。
公明党:日本が「子どもの権利に関する条約」を批准していることから、すべての子どもが教育を受ける権利を有することが定められており、仮に在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類で居住地等を確認するなど、柔軟な対応をもって、子どもたちの学びを確保すべきだと考えています。
立憲民主党:すべての子どもの学びの権利は、国籍や在留資格に関わらず憲法と子どもの権利条約で保障されるべきだと強く主張しています。
日本共産党・れいわ新選組・社民党:教育は子どもの権利であり、教育の機会は在留資格に関わらず、平等に保障されるべきだと主張しています。
参政党:「在留資格に関わらずすべての子ども」とは、合法的な在留資格を持つ外国籍の子どもを前提とする、と回答しています。すべての子どもに学ぶ機会があることは望ましく、就学を希望する者には教育機会が確保されるべきであると考える一方で、日本語能力が不十分な外国人児童が増え、学校生活への適応に支障をきたしているため、義務教育への就学に際しては、一定の日本語能力を要件とする制度整備が必要であると考えています。
7. 在留外国人の医療へのアクセス保障
在留資格に関わらず、在留外国人の医療へのアクセスを保障すべきかについては、各党で異なる見解があります。
日本維新の会:万人が平等に医療を受診する権利があるため、アクセスを保障すべきであると考えています。
日本共産党:医療へのアクセスは人権であり、在留資格に関わらず保障されるべきであると強く主張しています。
れいわ新選組:全ての人に対して基本的人権が保障されるべきであり、在留外国人の医療へのアクセスも保障すべきであると主張しています。
社民党:医療へのアクセスは基本的人権であり、国籍や在留資格の有無にかかわらず保障されるべきだということは、憲法や国際人権規約、国際条約に照らしても当然であり、国際的なスタンダード(世界基準)だと強調しています。
公明党:外国人が安心して医療を受けられるよう、医療機関での外国語対応や国民健康保険の適切な運用を図るべきとしつつ、社会保険料等の未納情報を在留審査に反映させ、在留管理の高度化を目指すとしています。
立憲民主党:外国人労働者とその家族を社会保障制度の担い手と位置づけ、制度参加を確保すべきとしつつ、財政や人道的な観点から慎重な検討が必要だとしています。
国民民主党:外国人の社会保険加入実態を調査し、運用の適正化など必要な対策を講じるとしています。
8. 人種差別禁止法の制定
人種差別禁止法の制定についても、各党の姿勢が異なります。
立憲民主党は、日本が国連人種差別撤廃委員会から再三にわたり厳しい勧告を受けていることを踏まえ、国際人権基準に立つ「包括的差別禁止法」を制定するとしています。
国民民主党は人種差別禁止法については肯定的な姿勢です。
日本共産党は、国連人種差別撤廃委員会からの勧告を受け、「包括的差別禁止法」が必要であると主張しています。
れいわ新選組と社民党も人種差別禁止法の制定について積極的な姿勢を示しています。社民党は、罰則規定のある差別禁止法をつくることを目指すと公約しています。
公明党は、これまでも障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消推進法、部落差別解消法など、様々な人権課題の解決に取り組んできたとし、引き続き個別法による差別解消に取り組んでいくとしています。
日本維新の会と参政党は人種差別禁止法の制定に対しては消極的または否定的な態度です。
9. 永住者などの定住外国人の地方参政権保有
永住者などの定住外国人への地方参政権付与についても、各党の見解は分かれています。
公明党:日本で生まれ育ち納税義務を果たしている永住外国人への地方参政権付与を国民の理解を得ながら丁寧に検討を進めるとしています。
日本共産党:永住者などの定住外国人への地方参政権付与は認めるべきであると主張しています。
社民党:地方自治の本旨は「住民自治」であり、納税・地域活動・子育てなど地域に貢献する外国人も「住民」として尊重されるべきで、国籍の有無ではなく、その人が地域社会の構成員かどうかが基準になるべきだと考えています。
日本維新の会は永住者などの地方参政権については消極的な回答を示しています。
参政党は、外国人参政権は一切認めず、帰化一世にも被選挙権を付与しない方針を明確にしています。
立憲民主党:永住者などの地方参政権については、党内で結論が出ておらず「どちらとも言えない」としつつも、多文化共生社会の実現を目指し、外国人の政治参加や地域の課題への意見反映のあり方を検討していくとしています。
国民民主党:永住者の増加が影響力の増加を意味することから、なし崩し的な環境整備ではなく、国としての明確な政策や計画が必要であるとしています。
れいわ新選組:永住者などの地方参政権については「無回答」です。
10. 外国人政策に関する司令塔組織
政府および一部政党は、外国人政策の一元的な管理やトラブル対処のため、司令塔組織の設置を検討しています。
自民党:石破総理は、外国人政策の司令塔組織を設置する方針を打ち出しています。林官房長官も、一部の外国人による犯罪や制度の不適切利用によって国民が不安や不公平感を有している状況があることを指摘し、在留外国人の犯罪などに対して政府一体で対処する組織を設置すると述べています。
参政党:外国人政策に関する理念法を整備し、「外国人総合政策庁」を新設して、関係各省庁と連携しながら、受け入れの基準や制度の運用を一元的に管理していくことを公約に掲げています。
日本維新の会:「外国人総合政策庁」の新設と理念法の整備により、管理型の外国人政策への転換を主張しています。
社会的な議論と識者の意見
外国人政策が争点になった背景
東京都議選で外国人に対する不法滞在の取り締まり強化などを訴えた参政党が躍進したことで、各党が外国人政策に力を入れ始めたと報じられています。これは、相次ぐ外国人の犯罪行為に不安を抱く有権者の支持が参政党に集まったとみられています。
「排外主義」への警戒
各党は「排外主義」と見られることへの強い警戒感を持っています。日本は急速な人口減少に直面し、労働力人口も減る中で、外国人の活力を取り込むことが不可欠な状況であるため、規制強化と共生のバランスを取ることに苦慮していると指摘されています。
SNS上の情報と実態
SNSでは、「外国人による犯罪が増えている」「外国人が日本の国民健康保険に加入して不正に医療を受けている」といった噂が拡散されています。
しかし、識者からは以下の指摘があります:
- 外国人の犯罪は割合として高いわけではなく、近年むしろ低下傾向にある
- 外国人の検挙人数は過去10年ほど横ばい
- 国籍ごとの犯罪率を見ても、中国、韓国、欧米出身者などは日本人と変わらない
- 外国人による不動産の買い占めについても、確固たる調査データはなく、冷静な検証が必要
専門家は、外国人を排除する政策は、経済規模の維持を困難にし、最終的には日本国民自身の権利抑制につながる危険性があると警鐘を鳴らしています。
大政党の責任
大政党は、これまで外国人に関するトラブル対策を怠り、共生政策の機能不全を放置してきた責任が大きいと指摘されています。また、少数政党の人気にあやかろうと、既存政党や政治家が少数政党まがいの発言をするのは危険で無責任であるとの意見もあります。
国民的議論の必要性
東京大学教授の永吉希久子氏は、外国人労働者の受け入れをなし崩しに進めるのではなく、国民的な議論を行うことが重要であり、その際は感情に訴えるのではなく、客観的なデータに基づいて冷静に議論する必要があると述べています。
各党のグラデーション
規制・管理強化を明確に打ち出す政党
参政党は「日本人ファースト」を掲げ、外国人労働者の無制限な受け入れに反対し、高度な技術・専門知識を持つ人材を優先し、日本語能力や文化的理解を義務付けるなど、国益を重視した管理型外国人政策への転換を明確に主張しています。
日本保守党は、入管難民法の改正と運用の厳格化、外国人を別立てにするための健康保険法や年金法の改正を掲げ、「野放図な移民政策を是正する」と訴えています。
共生・人権保護を重視する政党
社民党は「排除」より「共生」、外国人労働者の「搾取」より「平等な労働条件の保障」を基本方針とし、罰則規定のある差別禁止法の制定を求めています。
日本共産党は「排外主義を許さない」と強調し、外国人労働者への日本人と同等の権利保障や独立した難民認定機関の設置を主張しています。
立憲民主党は、外国人の人権を保護し、安心して働き生活できる環境を整備する「多文化共生社会」の実現を目指し、差別を禁止する法律の制定や在留制度全般の見直しを掲げています。
れいわ新選組は「移民政策」自体には反対し、労働者の安使いを問題視しつつも、外国人労働者への賃金差別の規制や、在留外国人の法制度を「管理」ではなく「権利の保護」へと改定することを主張しています。
両者のバランスを模索する政党
自民党は「ルールをきちんと守ろうよ」と外国人へのルール順守を訴えつつ、外国人とのトラブル解決や司令塔組織の設置を通じて、社会の不安に対応する姿勢を示しています。
公明党は、外国人材の受け入れの必要性を認めつつ、社会保険料未納情報在留審査への反映など「ルールを守らない方には、しっかりそのルールを守らせる厳格な運用」も掲げ、秩序ある共生社会を目指しています。
国民民主党は、当初の公約にあった「外国人に対する過度な優遇を見直す」という表現を「外国人に対して適用される諸制度の運用の適正化を行う」に修正するなど、「排外主義的だという批判」への配慮を見せつつ、居住目的でない住宅の取得への「空室税」導入検討や土地取得規制の厳格化を主張するなど、特定の側面での規制強化も検討しています。
日本維新の会は、外国人比率の上昇抑制や受け入れ総量規制を公約に明記していますが、同時に「万人が平等に医療を受診する権利がある」とも主張しており、バランスを取ろうとする姿勢が見られます。
まとめ
2025年参議院選挙における外国人政策は、日本の人口減少問題と労働力確保、社会の安定、そして人権保障という多岐にわたる側面から議論されており、各党がそれぞれ異なるアプローチを提示していることがわかります。
これらの各党のスタンスは、日本の人口減少と労働力不足という現実的な課題、外国人による社会問題への懸念、そして国際的な人権基準との整合性という複数の要因が絡み合う中で形成されており、有権者にとって重要な選択肢となるでしょう。
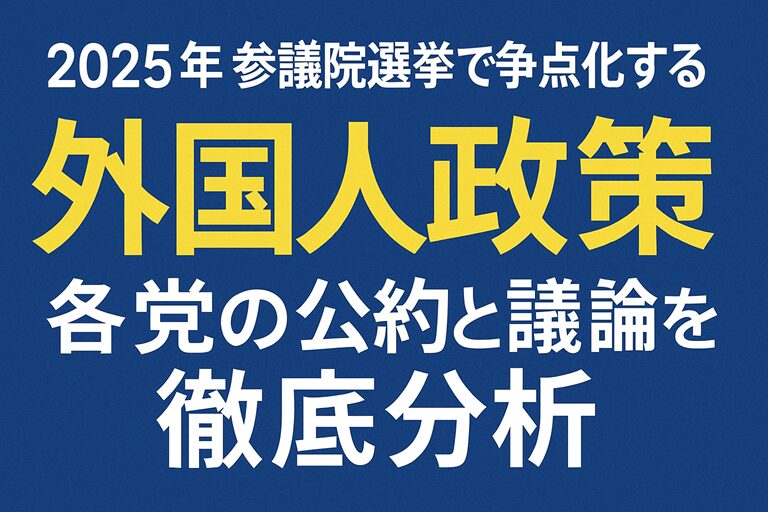



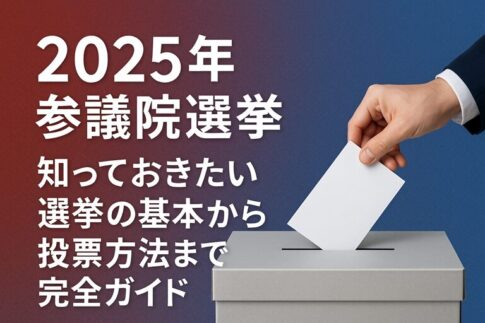
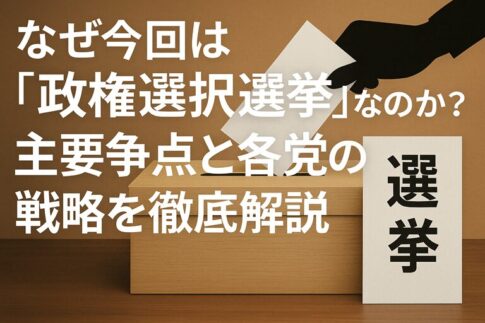

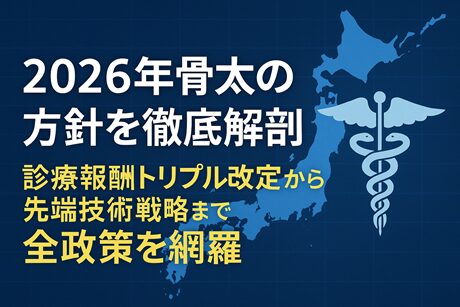


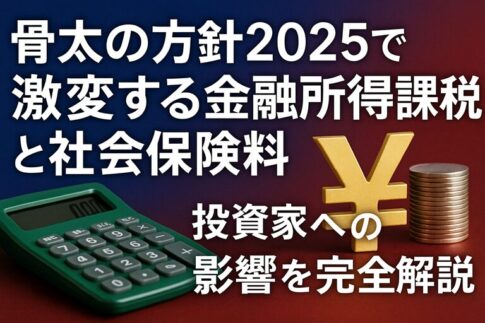

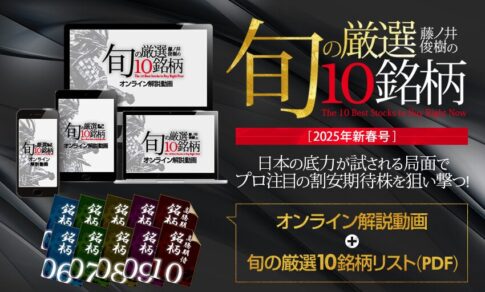








コメントを残す