目次
EU・米国通商交渉の全貌:10%関税受け入れの背景と産業別インパクト完全分析
欧州連合(EU)が米国との通商交渉において、輸出品の大半に10%の一律関税を受け入れる用意があることが明らかになりました。しかし、医薬品、アルコール、半導体、商用航空機などの重要セクターでは、米国に関税引き下げを確約するよう求めています。さらに、自動車・自動車部品への25%関税、鉄鋼・アルミニウムへの50%関税についても、割り当て枠や免除措置による実質的な関税引き下げを要求しています。本記事では、この複雑な通商交渉の全貌と、各産業への影響を徹底分析します。
トランプ政権の「相互関税」政策:戦後国際経済秩序への挑戦
2025年4月2日、トランプ大統領は「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の導入を発表しました。この政策は「米国を再び偉大に(MAGA)」という目標の一環として、貿易赤字の是正、国内産業の保護、不公正な貿易慣行への対応を目的としています。
相互関税の二段階構造
相互関税は以下の二段階構造を持っています:
- 基本関税:ほぼ全ての輸入品に一律10%(2025年4月5日発効)
- 追加関税:米国の貿易赤字が大きい特定の国・地域に対して、国別に11%から50%の追加税率を上乗せ
EUには当初、上乗せ分を含めて20%の関税が課される方針でした。しかし、2025年4月9日、米国は中国・香港・マカオを除く国・地域に対する国別相互関税の上乗せ部分を90日間(7月9日まで)一時停止し、その間は10%の基本関税が適用されることになりました。これは二国間交渉を促進する目的とされています。
注目すべきは、中国に対する扱いです。中国の報復関税発表を受け、段階的に関税率が引き上げられ、最終的に実効的な追加関税率は145%に達しました。さらに、中国と香港からの低価格(800ドル未満)輸入品に対するデミニミス免除は、2025年5月2日から撤廃され、複雑な代替関税が適用されるようになりました。
通商拡大法232条による追加措置:鉄鋼・アルミ・自動車への影響
鉄鋼・アルミニウム:25%から50%への引き上げ
2025年3月12日から、全ての国からの鉄鋼・アルミニウム製品に対し一律25%の追加関税が課されました。その後、2025年6月4日からは、英国を除くすべての国からの輸入製品に対する関税が25%から50%に引き上げられました。
米国政府は、国家安全保障上の理由から、国内の鉄鋼・アルミニウム生産設備の稼働率を80%に引き上げることを目指しています。この措置により、欧州の鉄鋼・アルミ部門は以下の影響を受けています:
- EU域内企業の輸出減少と損失拡大
- 追加関税の対象外であるアルミスクラップの米国向け輸出急増
- 域内リサイクル産業への打撃
- 循環型経済実現に向けた二次原材料確保への影響
スイスは過去の米国関税で第三国とみなされ、割り当て枠がすぐに埋まり、25%の関税に直面してEUへの輸出が困難になった経験があります。日本からの鉄鋼製品は、年間125万トンまで232条関税の適用が除外される関税割当(TRQ)が導入されています。
自動車・自動車部品:25%関税の衝撃
2025年4月3日から、米国は全ての輸入自動車に25%の追加関税を課しました。自動車部品についても5月3日までに同様の追加関税が予定されています。米国政府は国家安全保障と国内製造業保護を理由としています。
各国・地域への影響は以下の通りです:
ドイツ:ドイツの自動車産業にとって米国は重要な市場であり、米国向け輸出額の約22%(350億ユーロ、2024年)を占めます。特に米国に生産拠点を持たないポルシェのような企業は大きな影響を受けると指摘されています。
英国:米国は英国車について「年10万台を上限」に税率を10%まで引き下げ、それを超える部分は27.5%とする関税割当制度を導入することで合意しました。しかし、これは従来の2.5%の関税から実質的に引き上げられた形です。
カナダ・メキシコ:カナダは米国製自動車に25%の報復関税を課し、メキシコも米国からの輸入に25%の関税を提案しています。これらの関税は、自動車や機械の製造に必要な鉄鋼やアルミニウムの価格を大幅に引き上げ、消費者や企業のコスト増につながると予想されています。
日本:日本の自動車関税率は無関税ですが、他国では高関税がかけられている国が多く、米国はトラックに25%、中国は完成車に15%を課しています。日本のメーカーは米国内での生産拡大や雇用創出に貢献していますが、英国以上に低い税率を勝ち取れるかは不透明です。
重要セクター別の詳細分析
1. 医薬品:国民の健康か産業保護かのジレンマ
トランプ政権は、米国内の医薬品価格が他国に比べて高すぎることを問題視し、関税を課すことで他国との価格を「平等化」したいと表明しています。また、国内生産回帰を促す狙いもあります。
EU/スイス/日本への影響:
- EU:医薬品は対米貿易黒字品目の一つであり、アイルランドなどは米国向け医薬品輸出が特に多く、関税が課されれば経済的影響が懸念されます。アイルランドは法人税率の低さから多くの米国系製薬企業が拠点を置いており、そこで生産された医薬品を米国へ逆輸入する構造があります。トランプ政権はこのアイルランドの「税制スキーム」を問題視しています。
- スイス:製薬大手ロシュやノバルティスは、米国が世界的な利益の大部分を占めており、医薬品はスイスの輸出品全体の40%を占め、その6割が米国向けです。25%の関税が発動された場合、スイスの製薬会社は約87億5000万ドルのコスト増に直面する可能性があります。
- 日本:主要製薬企業の米国売上比率は高く(武田51%、アステラス41%、エーザイ31%など)、医薬品関税が現実となれば業績への打撃は避けられない構造です。
業界の対応と懸念:
製薬企業は、米国での生産拡大(リショアリング)やサプライチェーンの分散を模索しています。ロシュは既に米国での生産を増やし、他の企業も技術移転を進めています。しかし、短期間での大規模な生産拠点移転は困難であり、品質保証や認可取得に時間がかかることが指摘されています。
現在、米国で消費される医薬品の大部分は、原薬や重要な製造工程が海外で行われており、特にジェネリック医薬品はインドや中国で生産される傾向があります。インドの巨大なジェネリック医薬品産業も、その原料の多くを中国から輸入しています。
関税による調達コスト上昇が供給停滞を招き、医薬品不足や患者負担増大につながる懸念も高まっています。医薬品は国民の健康に直結する生活必需品であり、関税が上乗せされると価格上昇や供給不足につながる可能性があり、政治的な批判が高まるリスクがあります。
2. アルコール(ワイン、蒸留酒):200%関税の脅威
トランプ大統領は、EUが米国産ウイスキーに高関税を課す計画を発表したことを受け、EUからのワインやシャンパン、その他のアルコール製品に200%の関税を課すと警告しました。
EUの輸出への影響:
- EUの2024年のアルコール飲料輸出額は約298億ユーロ
- 最大の輸出先は米国(89億ユーロ、約30%)
- 特にワインは対米輸出の過半を占める
関税が実施された場合、EUのワイン業界にとって壊滅的な損失となると警告されています。フランスのシャンパン生産者は業界全体が破壊されると懸念を表明しました。
EUは当初の対抗措置からワインやジン、ウイスキーなどを含む品目を対象とする計画を発表しましたが、交渉により一部を対象外とした経緯があります。アイルランドやイタリア、フランスなどの加盟国の働きかけにより、ウイスキーやワインなどのアルコール飲料は対抗措置の対象品目リストから除外されました。
3. 半導体:戦略的重要性と技術覇権争い
半導体は、米国が国家安全保障と経済安全保障の観点から国内生産を重視している戦略的産業です。各国政府は自国のAIエコシステムの革新と拡大を目指しており、AIに関する自立性向上と地政学的に対立する国・地域に立地する関連サプライチェーンのデリスキングを進めています。
EUの目標:
EUも「デジタルコンパス2030」政策で、2030年までに次世代半導体生産高の少なくとも20%をEU域内で生産する目標を掲げ、米中に追いつくことを目指しています。
半導体とその原材料は引き続き輸出管理と投資奨励策の焦点となり、各国政府が国内生産を促進しています。ネットワークインフラの安全性とガバナンスも優先課題であり、敵対関係にある国に本拠地を置く企業への材料・部品供給禁止措置なども行われています。
4. 商用航空機:長年の補助金紛争
米国とEUの間では、航空機メーカー(ボーイングとエアバス)への補助金を巡る貿易紛争が長年続いています。
関連関税:
WTOがエアバスへの補助金を不当と判断したことを受け、米国は2019年10月にEUからの輸入品に年間75億ドル相当の追加関税を課す報復措置を発動し、民間航空機に10%(その後15%に引き上げ)を上乗せしました。これはフランス、ドイツ、スペイン、英国製の航空機が主な対象となりました。
EU側も対抗措置の候補リストを公表しましたが、「報復合戦は望まない」として、対話による解決を目指す姿勢を維持しています。
EUの対応戦略:外交優先と対抗措置の準備
EUは、米国の関税措置に対して慎重ながらも、必要に応じて対抗措置を取る姿勢を示しています。
対抗措置と交渉の姿勢
鉄鋼・アルミニウムへの対抗:米国が鉄鋼・アルミニウムに関税を課したことに対し、EUは2025年4月14日、総額210億ユーロ規模の対抗措置を官報に掲載しました。これは、当初4月15日から施行予定でしたが、米国の相互関税一時停止を受け、EUも7月14日まで適用を一時停止しています。
自動車・相互関税への対抗:EUは、米国の自動車・自動車部品への追加関税および一律10%の相互関税に対する新たな対抗措置の対象品目案を2025年5月8日に公表し、パブリックコンサルテーションを実施しています。英フィナンシャルタイムズ紙の報道によれば、米国が強みを持つITサービスを標的にする案も浮上しています。
交渉による解決の優先:EUは、米国との間で報復合戦がエスカレートし、貿易戦争へと拡大することを最も懸念しており、粘り強い交渉による解決に最大の優先順位を置いています。交渉が決裂した場合に備え、1000億ユーロ相当の米国製品を関税の標的とする対抗措置の計画を公表しています。
戦略的自律性の強化:EUは、過度な対外依存を脱し経済安全保障を強化するため、「クリーン貿易・投資パートナーシップ」の締結や重要セクターにおける欧州企業優遇、循環型経済の推進などを目指しています。
EU経済への影響
GDPの下押し:米国の関税政策はEU経済に大きな打撃を与えると予想されており、直接効果と間接効果を合計したGDPの下押し幅はEU全体で約-0.7%と試算されています。特にドイツやアイルランドなど、製造業の比重が高い国や対米依存度が高い国で影響が大きくなると見られています。
物価への影響と中国製品の流入:関税は輸入品価格を押し上げる一方で、世界各国の米国向け輸出が欧州市場に再配分され、競争が激化することで、EUの物価が下押しされる可能性も指摘されています。
企業景況感の悪化:米国との通商摩擦の過熱は、企業の景況感や投資判断に悪影響を及ぼす可能性があります。
欧州企業の対応策:地政学的変化への適応
欧州企業は、米中間の貿易摩擦や広範な地政学的緊張、そして各国の経済主権強化の動きに対し、サプライチェーンや生産拠点の戦略を多角的に変更しています。
サプライチェーンの多様化と生産拠点の再編(デリスキング)
- 多くの政府が経済的優位性と主権を保全するため、保護主義的な貿易政策や産業政策を強化しており、これに伴い企業はサプライヤー拠点の多様化を進める可能性があります。
- デジタル技術や気候関連技術といった戦略的セクターにおいて、国内生産を奨励または義務化する産業政策が導入され、企業はこれに関連する税制優遇措置や補助金、政府保証付き投資の機会を模索しています。
- グローバル製造企業は、サプライチェーンの分散化を進める中で、人材のスキルや獲得可能性を代替立地の評価軸として考慮し、中央ヨーロッパや東ヨーロッパへの事業拠点の移転や事業運営の変更を検討しています。
- 多国籍企業の多くは、サプライチェーンの一部を東南アジア、インド、欧州・中南米の新興国に移転すると見られています。東南アジアは特に、外国直接投資(FDI)の主要な目的地となっています。
- モビリティ・宇宙・防衛セクターの企業は、サプライチェーンが長大であるため、原材料や部品の組み立てにおいて、オンショアリング(自国回帰)、ニアショアリング(近隣国への移転)、フレンドショアリング(友好国への移転)を優先的に検討しています。
具体的な企業の対応事例
米国市場における戦略事例:
- 環境分野:スペインのシーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー(SGRE)は、米国最大の洋上風力発電プロジェクトにおいて、優先タービンサプライヤーに指名されました。
- 自動車分野:
- フォルクスワーゲン(VW)は、米カリフォルニア州に自動運転の研究開発を行うコンピテンスセンターを開設し、2022年から米テネシー州のチャタヌーガ工場で、MEBプラットフォームをベースにした次世代の電気自動車(EV)の生産を開始する計画です。
- BMWは、米サウスカロライナ州の工場に約1,000万米ドルを投資し、車載充電池の生産能力を2倍に拡大しました。
- フロイデンベルクは、米国のリチウムイオン電池メーカーであるXALTエナジーを買収しました。
- ヘルスケア:フィリップスは、UVMヘルス・ネットワークと提携し、包括的な臨床およびビジネスソリューション、コンサルティングサービスを提供しています。
中国市場における戦略事例:
- 公共事業:
- アルストムは、中国で地下鉄および路面電車用のシステムを受注しました。
- シーメンスは、北京で中国国有電力大手の国家電力投資集団(SPIC)と包括的な戦略提携を締結しました。
- 化学産業:BASFは、湛江市に統合生産拠点(フェアブント拠点)を建設しており、基礎化学品から消費者に近い製品・ソリューションまでを連携する統合的なバリューチェーンを構築します。
- 電気自動車(EV):
- ドイツポストDHLは、電動小型商用車を開発・生産する子会社ストリート・スクーターの中国市場参入を発表しました。
- BMWグループと長城汽車(GWM)は、江蘇省の張家港市で電気自動車の合弁工場建設の鍬入れ式を行いました。
- ABBは、中国の充電設備メーカーである上海チャージドット新能源科技へ過半数出資を決定しました。
- コネクテッドカー:BMWとテンセント(騰訊控股)は、北京でデータセンター「BMWグループ・チャイナ・ハイパフォーマンス・D3プラットフォーム」の構築に関する合意書に署名しました。
2025年の地政学的動向と企業への影響
EYのレポートによると、2025年の地政学的動向を駆動する3つの主要テーマがあります:
1. 各国リーダーの軸足が選挙から政策へ移行
世界的な選挙イヤーであった2024年には、一部の国でポピュリズム的政策の支持者や反主流派が勢力を拡大しました。これにより、2025年には保護主義政策の強化、移民制限、グリーン政策への圧力、政府機関の弱体化などの動きが高まることが予想されます。
2. 各国による経済的な競争と経済主権の強化
2024年に高まったデリスキング(リスク低減)の動きは2025年も続き、各国政府は経済主権強化のため保護主義的貿易政策や産業政策を拡充すると見られます。特にデジタル技術や気候関連技術が政策上最も重要な分野となるでしょう。
3. 地政学的対立の激化
世界的な多極化が進む中で、クロスボーダービジネスに適用される基準やシステムが複数策定され、競合することで世界経済の複雑化が進むことが想定されます。
2025年に予想される地政学的動向トップ10
- ポピュリズム政策の影響:経済格差の拡大、移民問題への脅威認識、国民としてのアイデンティティー問題などがポピュリストの訴えを加速させています。
- 課税に関する難題:多くの国で重い債務負担と財政赤字が増大しており、富裕層や企業への増税、課税の抜け穴封じ、徴税の効率化が進められる可能性があります。
- 人口動態からみえる分断:移民受け入れ国では、特定の専門技能を持つ人材を呼び込む一方で、移民制限がポピュリストの優先事項となる可能性があります。
- デリスキングと依存関係:保護主義的な貿易・産業政策はポピュリズム政権の優先事項となり、米国が先行して導入すると予想されます。
- デジタル主権:各国政府はAIエコシステムの革新・拡大を目指し、AIの自立性向上と関連サプライチェーンのデリスキングを進めます。
- 気候政策と競争:気候政策は環境保護主義に反対する思想や短期的な家計負担への経済的懸念から圧力を受ける可能性があります。
- 地政学的エネルギーに関する新たな力学:各国政府はエネルギー政策に関し、それぞれの理念、資源の利用可能性、地政学的協力関係に基づき、様々なトレードオフを行います。
- 新興国市場の統合:主要国の経済安全保障政策が新興国市場の投資計画の主な推進要因となるでしょう。
- 戦争と紛争:ウクライナでは物理的戦闘とサイバー領域の両面で戦争が継続し、中東では暴力行為の連鎖が続く可能性が高いです。
- 宇宙政治と宇宙経済:宇宙資源を巡る競争が鉱業企業に新たな投資と成長機会をもたらすと予想されます。
日本企業への影響と対応策
日本との交渉においても、10%の基本税率の撤廃については楽観視できない状況であり、上乗せ税率(14%)は日本の譲歩次第で削減される可能性があります。日本政府は貿易協定との整合性について懸念を示し、見直しを求める一方で、報復措置のような「売り言葉に買い言葉」は避ける姿勢です。
製薬産業への影響
日本の主要製薬企業(武田、アステラス、第一三共、中外など)は、米国売上比率が高く、医薬品関税が現実となれば業績への打撃は避けられない構図でした。幸い、トランプ政権下では医薬品が関税の「聖域」として最後まで除外されたため、巨額の関税を支払う事態には至っていません。
しかし、各社はサプライチェーンの冗長化(米国内製造拠点の拡充、多地域での生産体制確保)や在庫戦略の見直しなど、リスク管理を強化しました。例えば:
- アステラス製薬:米国ノースカロライナ州の遺伝子治療薬新工場建設
- 中外製薬:ロシュと提携し、必要に応じて一部製造を米国内にシフトする可能性を警戒
鉄鋼産業への対応
日本の鉄鋼製品に対しては、米国が4月1日から関税割当(TRQ)を導入しました。これはEUとの合意と同様の措置であり、年間125万トンまで232条関税の適用が除外されます。米国側は、中国の不公正貿易慣行に対する同志国連携を促進するものと強調しています。
経済安全保障とデカップリング
米国は、第三国(特に中国)による「非市場的政策」への対応を含め、経済安全保障に関する協力を同盟国に強化することを求めています。具体的な協力分野には以下が含まれます:
- 輸出管理
- 投資の安全保障措置
- ICTベンダーの安全性確保
- 知的財産権の保護
- 強制労働への対応を含む労働問題
- 環境
- 政府調達
- 迂回輸入防止のための税関協力
日本は、米国市場へのアクセス改善と引き換えに、供給網の安全性確保(例:中国資本や中国製品の一部排除)を要請された場合、難しい選択を迫られる可能性があります。これを拒否すれば関税削減が困難になり、受け入れれば中国による報復措置や経済のブロック化が進むリスクがあります。
企業がとるべき地政学的行動・対応策
経営幹部は、将来の不確実性に対するレジリエンスを強化し、ステークホルダーと積極的に関わり合いながら戦略を形成・維持することが求められます。
1. 戦略的な洞察力を働かせ、将来の不確実性に対するレジリエンスを強化する
- シナリオ分析や机上演習などの戦略的先見手法を活用し、不確実性を体系的に管理し、戦略的意思決定における自信を高める
- デジタルおよびテクノロジー関連のサプライチェーンを再評価し、オンショアリング、ニアショアリング、フレンドショアリングの動向に対応する
- デジタル主権に関連する投資機会を評価し、AIアルゴリズム、半導体、ネットワークインフラの研究・開発・製造を推奨または義務付ける産業政策に注目する
- 一貫性を欠く気候政策が国境を跨ぐ事業の相互運用可能性やサステナビリティ戦略に及ぼし得る影響を精査する
- エネルギー転換が企業の戦略やコンプライアンスに与える影響を認識し、投資判断において再生可能エネルギーの利用可能性と魅力度を検討する
- 最大のビジネス機会をもたらす新興国市場を分析し、市場の参入・拡大あるいは撤退の最適なシナリオを検討しておく
2. ステークホルダーと積極的に関わり合いながら戦略を形成・維持する
- 社内外の機微な政治的課題に対処するためのコミュニケーション戦略を策定し、地政学的動向に起因する事業リスクやレピュテーションリスクを軽減する
- 貿易・産業団体、投資家などのステークホルダーと協力し、潜在的な税制改正の影響を明確化しつつ、政府が効率的な税制政策を形成するのを後押しする
- 移民の経済的妥当性を政府に訴え、人材の獲得と維持につながる柔軟な労働移動の枠組みの設立を後押しする
- 政府債務の変動を財務計画に反映させ、シナリオに基づく計画や緊急時対応計画を策定する
- 戦略セクターにおける国内生産奨励策や政府保証付き投資機会を活用する
- サプライチェーンの多様化を進める中で透明性の担保を優先事項とし、地政学的リスクを軽減できない可能性も考慮に入れる
- 貿易制限や関税の急増に対応して、グローバルな取引戦略およびサプライチェーン全体の資金関係を再評価する
- 将来の紛争シナリオに対するレジリエンスを強化するため、事業拠点の移転や事業運営の変更について実行可能性を見極める
- サイバーレジリエンスに投資し、バリューチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを評価する
- 制裁リスクとコンプライアンスを把握し、評価する
全体的な経済・地政学的展望
不安定性と不確実性:近年の激しい戦争や紛争、経済関係の不確実性、そして破壊的要因(生成AIの進化、人口構造の変化、気候変動)が、2025年の世界経済と地政学的状況を形成する主要な要素となります。企業のサプライチェーンはますます複雑化し、不確実性への備えが重要となります。
デカップリングと経済ブロック化:各国政府は、国家安全保障と経済的目標を戦略的に融合させ、重要物資の国内生産拡大を目指す動きを加速させており、経済の流れが地政学的な線引きによって分断されたり、「コネクター国」によって経路が変更されたりしています。これにより、国際的な経済ブロックと同盟国のネットワーク間での競争と緊張が強まり、エネルギー転換のためのテクノロジーコストが増大し、導入が鈍化する恐れがあります。
多国間機関の機能不全:WTOの紛争解決機関が機能停止に陥っている状況では、米国の追加関税措置が国際法違反であっても、その抑止力にはなりにくいと見られています。
労働力と移民問題:多くの国で高齢化が進み労働力人口が減少する一方で、新興国では若年層の就業機会が不足し、社会不安や政情不安、越境移民のリスクが高まっています。移民の受け入れは労働力不足解消に繋がる可能性がありますが、受け入れ国では社会の分断を招く政治問題となっています。
財政負担:高齢化に伴う医療費や年金による財政負担が増大する中、年金支給額の引き下げや増税などの支出削減策が導入される可能性があり、これが社会不安を増大させるリスクがあります。
世界経済への全体的影響:IMF、WTO、OECDなど主要な国際機関は、米国の関税措置が世界経済成長予測を下方修正させ、インフレ圧力の高まりや景気後退リスクの増大を警告しています。金融市場は大きく動揺し、政策の予測不可能性が企業活動や投資判断の重石となっています。米国の関税措置が米国自身の経済に与える負の影響が大きいとの分析も多く、政策の意図と結果の乖離が懸念されます。
まとめ:新たな通商秩序への対応
EUは米国との貿易交渉において、一律関税の受け入れと引き換えに、自国の重要産業を守るための譲歩を引き出すことを目指しています。しかし、米国の強硬な交渉姿勢と、世界経済全体の不確実性が、その道のりを困難にしています。
企業にとっては、この歴史的転換期において、地政学的リスクを適切に評価し、サプライチェーンの多様化、現地化の推進、戦略的提携の強化など、多面的な対応が求められています。同時に、急速に変化する政策環境に対応できる柔軟性と、長期的な競争力を維持するための戦略的視点の両立が、今後の企業経営の鍵となるでしょう。
通商交渉の結果は、単に関税率の問題にとどまらず、21世紀の国際経済秩序の形成に大きな影響を与えることになります。各国政府、企業、そして市民社会が、この新たな環境にどのように適応していくかが、今後の世界経済の方向性を決定づけることになるでしょう。
関連記事:
- トランプ関税が日本の自動車産業に与える影響2025年版
- トランプ関税と日本のコメ問題
- 米国経済2025年:トランプ関税が日本に与える影響
- トランプ関税2025年の世界的影響
- トランプ関税と日本の自動車産業
- 米国24%関税が日本に与える影響
外部参考リンク:
- 世界経済評論インパクト
- 地経学研究所
- CNBC – Trade War Analysis
- Siemens Press Release
- BMW Group Press
- ABB News
- LVMH Press Release


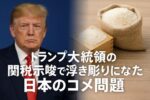
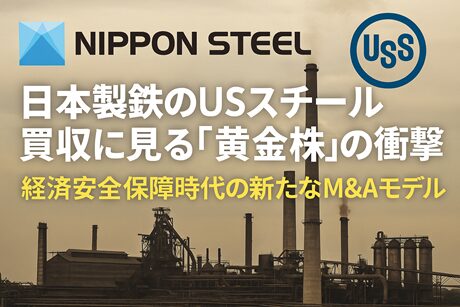
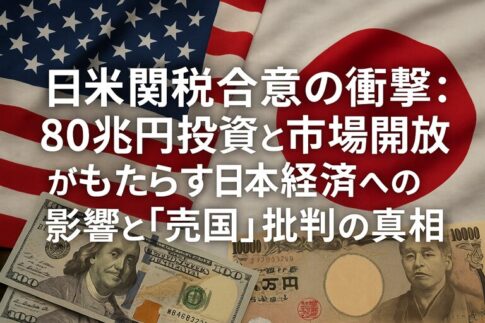
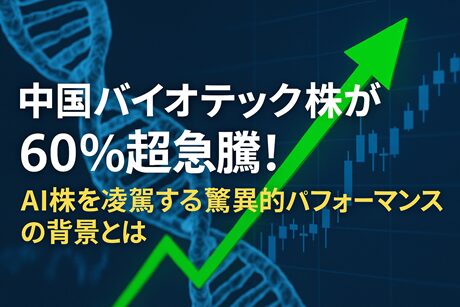


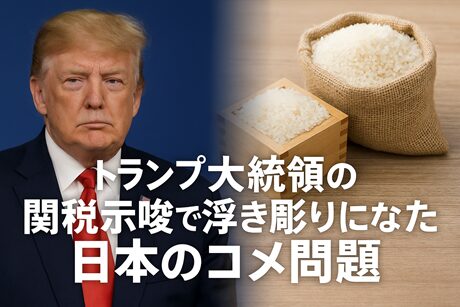



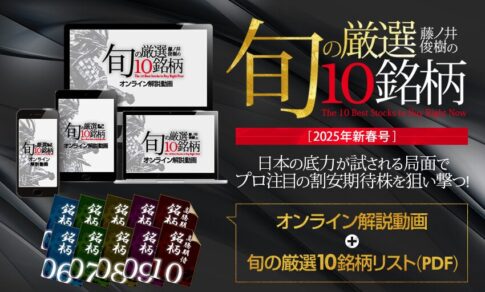





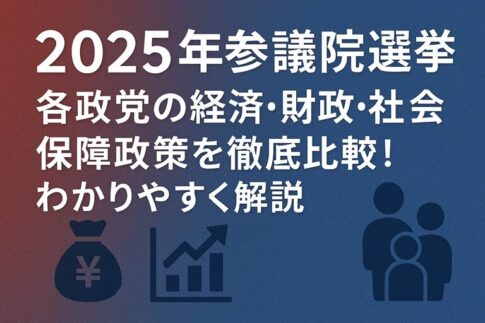


コメントを残す