目次
- 1 トランプ関税7月9日期限迫る – 赤沢大臣の米国交渉難航、日本への24%関税で自動車産業に数千億円の打撃か
トランプ関税7月9日期限迫る – 赤沢大臣の米国交渉難航、日本への24%関税で自動車産業に数千億円の打撃か
2025年7月9日午前0時1分(米国東部時間)、トランプ政権が発表した相互関税の90日間猶予期限が到来する。日本には24%の関税が課される予定で、特に自動車産業への影響は年間数千億円規模に達すると試算されている。赤沢亮正経済再生担当相は滞在を延長して交渉を続けているが、日米間の立場の隔たりは大きく、交渉は難航している。本記事では、トランプ政権の関税政策の全貌と、日本企業が直面する課題、そして今後の展望について、最新の情報を基に徹底解説する。
トランプ政権の相互関税政策 – 「アメリカファースト」の具現化
相互関税(Reciprocal Tariffs)とは何か
トランプ政権が2025年4月3日に発表した「相互関税」は、米国の貿易相手国が高い関税や非関税障壁を課している場合、米国も相手国と同じ水準まで関税を引き上げるという追加関税措置である。この政策は多くの国から妥当性について批判を受けているが、トランプ大統領は「公平な貿易」の実現を主張している。
関税率は概ね「貿易赤字額÷輸入額÷2」に基づいて算出されており、対米貿易黒字が大きい東アジアや東南アジア諸国に高い関税が課される傾向がある。相互関税の対象になるのは、米国における(メキシコ・カナダを除く)輸入総額の約7割程度と見込まれている。
法的根拠 – 国際緊急経済権限法(IEEPA)の活用
この政策の法的根拠は、1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)である。IEEPAは、大統領が国家安全保障、外交政策、または経済に対する「異常で重大な脅威」を宣言した場合に、貿易規制などの権限を行使できる法律だ。トランプ大統領はこれを活用し、以下の理由を挙げて関税措置を正当化している:
- 不公正な貿易慣行が米国経済を弱体化させている
- 自動車や造船などの先端産業における国内製造能力を維持する必要性
- 過度な輸入を是正し、米国の輸入を減らし輸出を増やす
- 貿易相手国による賃金や消費の人為的抑制
- 不法移民や医療用麻薬フェンタニルなどの違法薬物流入の阻止(カナダ・メキシコ向け)
しかし、米国際貿易裁判所(CIT)がIEEPAに基づく各種追加関税を「違法」と判断するなど、司法の壁も立ちはだかっている。カリフォルニア州を含む複数の州政府も同様の訴訟を起こしており、関税政策の法的基盤は必ずしも盤石ではない。
トランプ関税政策の時系列 – エスカレートする貿易戦争
2025年1月から6月までの関税政策の推移を見ると、段階的にエスカレートしていることがわかる:
2025年1月20日:トランプ大統領就任。当日の関税賦課は見送られたが、米中経済貿易協定の履行状況調査を命令。TikTokの禁止措置は75日間延期。 2月2日:中国からの輸入品に10%の追加関税を課す大統領令に署名(2月4日発動)。中国は石炭や液化天然ガス(LNG)などに報復関税。 3月4日:メキシコ・カナダへの25%関税が発動。中国への関税はさらに10%上乗せされ合計20%に。中国は米国産農産物などに報復関税を発動。 3月12日:中国や日本を含むすべての国から輸入する鉄鋼製品とアルミニウムを対象に25%の関税を発動(相互関税とは別枠)。 4月3日:世界各国への相互関税を発表。日本24%、中国34%、インド26%、韓国25%、EU20%、ベトナム46%など。 4月9日:相互関税第2弾発動。中国への関税は50%上乗せされ合計104%に。中国も対抗し、米国からの輸入品全ての関税を84%に引き上げ。 4月10日:中国への関税は125%に引き上げ(既存の20%と合わせて145%)。中国を除く世界各国への相互関税第2弾(10%を超える部分)は90日間停止。期限は7月9日午前0時1分。 4月11日:スマートフォンやコンピュータなど電子機器20品目が対中相互関税から適用除外。赤沢亮正経済再生担当相 – 石破首相の「左腕」が挑む国難
異例の抜擢と重責
赤沢亮正氏は1960年生まれの64歳。東京大学法学部を卒業後、旧運輸省(現国土交通省)に入省した。2005年の衆議院選挙で初当選し、現在は7期目を務めている。石破茂首相の側近中の側近として知られ、赤沢氏自身は石破氏を「石破さんの左腕」と称し、「趣味石破茂」と公言している。石破氏も「タバコと赤沢はやめられない」と言うほど、赤沢氏に全幅の信頼を置いている。
昨年の自民党総裁選では、石破陣営の事務総長として指揮を執り、石破氏の総裁就任に貢献した。非常に生真面目で細かい性格で、官邸に「赤沢部屋」と呼ばれる場所で霞が関からの要望に目を通し、石破氏が興味を持つか、さらに調査が必要かなどを判断する門番的な役割を担っていた時期もある。
現在の担当は経済再生、新しい資本主義、賃金向上、スタートアップ、全世代型社会保障改革、感染症危機管理、防災庁設置準備、そして内閣府特命担当大臣(経済財政政策)と多岐にわたる。
外交経験の不足と交渉役選任の背景
官僚時代に旧運輸省の国際航空課で日米航空交渉に携わった経験はあるものの、議員になってからは閣僚経験がなく、政府代表として外交を行った経験はこれまでなかった。自民党内では、官房長官の林義政氏(英語堪能、海外経験豊富)や、2019年の日米自由貿易協定交渉でトランプ氏から「タフネゴシエーター」と称された茂木敏充元幹事長(英語堪能、経済産業関係に精通)などが有力候補として挙がっていた。
しかし、最終的には石破首相と赤沢氏の強い信頼関係が選任の大きな理由だったとされている。赤沢氏自身も当初は交渉担当としての指名に弱音を吐いていたようだが、近しい人々に「なんとかこの国難を打破したい、大変な重責ですが頑張ります」と語るほど意気込みを見せていた。
交渉の経過と難航する協議
赤沢大臣の訪米と交渉の主な経過は以下の通りである:
4月16-18日:訪米し、ホワイトハウスでトランプ大統領と面会。これは閣僚としては異例であり、日本人としては総理と大谷翔平選手に次ぐ3人目の執務室での面会と報じられた。 6月16日:G7サミット中の日米首脳会談。しかし会談時間は30分と短く、関税に関する合意は「協議継続」のみにとどまった。石破首相は「双方の認識は一致していない」と述べている。 6月27日:ワシントンでラトニック商務長官と約65分間対面で会談。貿易拡大、非関税措置、経済安全保障面での協力について「実りある議論を行った」と日本側は発表。 6月28日:ラトニック商務長官と2回電話協議(夜に約15分間、29日朝に約20分間)。 6月29日:当初の帰国予定を延長し、ベッセント財務長官とのさらなる協議を模索するも実現せず。 6月30日:帰国予定。交渉では、米国が輸入自動車に課している25%の追加関税の引き下げ(撤廃)が議論の焦点となっている。日本側は、自動車関連で米国に600億ドル(約9兆円)以上の投資を行い、230万人の雇用を生み出していることを挙げ、25%の自動車関税は受け入れられないと主張している。
しかし、日米間では自動車関税を巡る立場の隔たりが大きく、交渉は難航している。ベッセント財務長官との直接協議は実現せず、この一連の交渉に対しては、インターネット上で「相手にされてない」「成果なし」といった厳しい意見も出ている。
日本への影響 – 自動車産業を中心に広がる懸念
自動車産業への甚大な影響
トランプ政権の関税政策は、日本の自動車産業に特に大きな試練をもたらすと予想されている。米国新車市場の約半分(48.6%)が輸入車で、日本からの輸入が17%を占めている(2024年データ)。米国国際貿易委員会(USITC)の2024年のレポートでは、北米以外からの輸入品に25%の関税がかかると、自動車輸入が73.9%減少し、米国内の自動車平均価格が5%上昇すると試算されている。
具体的な影響として以下が挙げられる:
1. 輸出収益の減少と価格競争力の低下- 対米輸出が大幅に減少し、年間で数千億円規模の影響が予想される
- 米国市場での日本車の価格が上昇し、他国メーカーとの競争において不利になる
- 消費者が価格上昇を嫌い、米国国内製品や他国メーカー製品に乗り換える可能性が高まる
- 自動車産業は日本国内で数百万人の雇用を支える基幹産業
- 愛知県では県内雇用の約20%が自動車産業と関連しており、トヨタ自動車の国内生産削減は部品メーカーやサプライヤーの経営悪化に直結
- 群馬県太田市のように自動車関連工場が地域の主要雇用源となっている都市も同様に影響を受ける可能性
- 完成車メーカーだけでなく、部品供給を担う中小企業や物流業者など、幅広い業種にわたって影響が及ぶ
- トランプ政権の政策は米国内での生産を奨励しており、日本の自動車メーカーは部品供給体制の再構築を迫られる
- 部品輸送コストの増加やグローバルサプライチェーンの効率性低下のリスク
- サプライチェーンの変更は、製品の品質や開発スピードにも影響を与え、大幅なコスト増加や開発期間の延長を招く可能性
- 最終的に消費者が購入する車両の価格にも影響が出て、メーカーの収益を圧迫しかねない
メーカー別の影響度と対応
日本の自動車メーカーの米国での生産比率や「稼ぐ力」によって関税負担額と営業利益の比較で影響度が異なる:
- 三菱自動車:全量輸入に頼っているため影響が最も大きい
- トヨタ・ホンダ:米国生産比率が高く、影響が比較的低い
- マツダ:2025年に入り対米輸出は好調
- 日産:対米輸出が不振
関税コストは最終的に消費者に転嫁され、製品の値上げにつながる可能性があるが、トランプ大統領は関税を理由にした価格改定を「好ましくない」と牽制しており、トヨタも当面値上げしない方針と報じられている。大企業の自動車メーカーは、関税を自腹で賄っていく余力があるため、米経済の再拡大を待ってから値上げを順次進めることで、国内へのデフレ圧力を回避できる可能性がある。
自動車産業以外への影響
相互関税の対象品目には以下も含まれる:
- 日本酒:相互関税の対象品目に指定
- 牛肉:日米貿易協定による低関税枠が2025年分で上限に達しているため、枠外適用になる可能性
- 化学品:相互関税の対象品目に指定
- 一次金属産業:中間財輸出減少により影響
- 情報通信関連財産業:サプライチェーンを通じた影響
- 卸売・小売業:貿易動向に敏感で影響を受けやすい
- 食品加工業:0.6%減と予測
各国の交渉状況 – 期限迫る中での駆け引き
7月9日の期限を前に、各国も対応に苦慮している。主要国の状況は以下の通り:
中国 – 最も厳しい関税と報復合戦
中国は既に125%の関税が課されており(既存の20%と合わせて145%)、これ以上の関税引き上げは実質的に意味がないとして対抗しない姿勢を示している。ただし、レアアースの輸出規制を行い、米国の自動車生産に影響を与えた。2025年6月にはロンドンでの通商協議で、中国がレアアース輸出規制を解除する代わりに、米国は一部の輸出規制緩和や中国人留学生受け入れで合意したと発表されている。
米国側が対日交渉に消極的な背景には、中国との貿易交渉(特にレアアース問題)に多大なエネルギーを投入している現状がある。
インド – 26%の関税に直面
インドの通商交渉団も、米国との二国間貿易協定(BTA)交渉を進めており、7月9日の期限までの合意を目指してワシントンでの滞在を延長している。インドメディアによると、インドは自動車部品など重要産業の無関税化を望んでいたが、米国側が応じず協議は停滞していると報じられている。
一方で、米印当局間の貿易交渉は前向きに進展しており、ベッセント米財務長官はインドが最初に発表される貿易協定になるかもしれないと述べている。IMFと世界銀行は、2025年度のインドの経済成長率予測を下方修正しており、その下振れ要因として、米国の関税政策に伴う世界貿易の縮小を指摘している。
韓国 – 25%の関税で協議継続か
韓国は日本より高い25%の相互関税が迫っている。4月の最初の協議では7月までに協定を結ぶことで合意したが、ヨ・ハング通商交渉本部長は「7月の期限にこだわらない」と述べ、期限以降も協議を続ける可能性を示唆している。
ベトナム – 46%という高関税に直面
ベトナムは日本の倍近い46%の相互関税が課される状況だが、ファム・ミン・チン首相は「2週間以内に結果が出るよう期待している」と述べ、ベトナムと米国は関税について深い理解を共有していると自信を見せている。
EU・英国 – 比較的低い関税率
EUは20%、英国は10%と、アジア諸国に比べて相対的に低い関税率が設定されている。これは対米貿易黒字の規模が影響していると考えられる。
期限延長の可能性と「報復税」という新たな脅威
7月9日期限の行方
ベッセント財務長官は、7月9日の期限を9月1日まで延長し、協議を続ける考えを示唆している。彼は、主要な貿易相手国18カ国のうち10~12カ国と合意できれば9月1日までに交渉をまとめられると述べている。
しかし、トランプ大統領は6月27日の記者会見で「期限を延長する必要はない」との考えを示し、「延長も、短縮もできる。私は短縮したい」と述べ、交渉の主導権はあくまで米国にあることを強調している。また、今後1週間半~2週間以内に、相手国に対して一方的に関税率を設定する「書簡を送付する」と繰り返し示唆している。
ホワイトハウスのレビット報道官も、7月9日の期限は「絶対的なものではない」とし、延長の可能性に言及しているが、合意が得られない国には「米国にとって有利な相互関税率」を設定するディールを提示できるとも述べている。
米国商工会議所は、今後6カ月間で追加関税率は現在の水準よりも高くなるものの、4月に発表された相互関税率(高水準)が適用されるほど高くはならないと予測している。現時点(6月末)で期限内の合意は英国との1件のみという状況だ。
「報復税」という新たな法案
関税の猶予期限が迫る中、「報復税」と呼ばれる新たなトランプ政権の法案が波紋を呼んでいる。これはトランプ政権が掲げる「大きく美しい法案」の中に記載されており、米国が不公平な税制とみなした国の企業や投資家を対象に、米国で得た収益に対して毎年5%の税(上限あり)を課すというものだ。
米国は、日本でも来年度から始まる法人税の国際的な枠組みを敵視しており、日本企業もこの追加課税の対象になる可能性がある。ベッセント財務長官は、G7が米国が問題視する法人税の枠組みから米国を除外したため、「報復税を大きく美しい法案から取り除く」よう議会に要請したとSNSで投稿している。
トランプ大統領の真意と交渉の焦点
自動車貿易への不満
トランプ大統領は、日本との自動車貿易が不公平であると繰り返し不満を表明している。米国が日本から多くの自動車を輸入している一方で、米国から日本への輸出が少ないため「公平ではない」と主張している。貿易赤字削減のため、日本が米国産のエネルギー資源(原油、アラスカLNGなど)やその他の製品の購入を増やすべきだとの考えを示している。
アラスカLNGはUSスチール以上の「超政治案件」となる可能性が指摘されている。トランプ氏は、日本側に対し、自動車への関税を25%だと書簡で通告することも可能だという認識を示し、容易に譲歩するつもりはない姿勢を改めて示している。
政策の不確実性と「迷走」
トランプ政権の関税政策は、金融市場の安定に配慮して一時停止されたり、報復措置の応酬の後に引き下げられたりするなど「迷走を続けている」と評価されることがある。政策は予測が難しく、SNSなどで突発的に発表されることも多いため、企業は個々の政策を「実行可能性」「影響が出るまでの期間」「影響が続く期間」の観点で分析し、対応を検討する必要がある。
「ブーメラン効果」と世界経済への影響
米国自身への最大の打撃
保護主義的な通商政策は、意図した効果を生まず、実施国である米国において最も大きな影響が出る「ブーメラン効果」が指摘されている。関税によって輸入物価が上昇し、これが起点となって経済活動が悪化することで、結果的に日本からの輸出や国内生産も減少すると見られている。
日本の実質GDPへの総合的な影響は最大で1.4%程度の減少が見込まれている。特定の産業では、自動車産業が1.7%減、食品加工業が0.6%減と、大きな負の影響を受けると予測されている。
スタグフレーションのリスク
関税引き上げが7月9日の期限通りに実施され、同時に米国の軍事介入に伴う原油高騰が重なると、世界経済がスタグフレーション(不況とインフレの併存)に陥る可能性が懸念されている。短期的には需要急減と供給過剰によりデフレ圧力となる一方、中長期的には経済合理性に基づくサプライチェーンの見直しが生じることで、世界的な製造コストを押し上げると見られている。
WTOの機能不全
トランプ政権の関税政策は、日本と米国の貿易関係に緊張をもたらし、WTO(世界貿易機関)の機能停滞を招いている。本来、WTOの場で国際ルールに基づく解決が図られるべきだが、米国のWTO軽視姿勢や組織内部の対立により、仲裁機能が十分に機能していない。
米国は、上級委員会の判断が事実上の先例となり協定解釈を拡大していることなどに不満を募らせ、委員の選任を拒否し続けている。WTO紛争解決は長期化し、機能停止状態にある。
日本企業の対応策 – 短期と中長期の戦略
短期的対応策
1. 情報収集と分析の強化- 米国のロビー活動企業や法律事務所、コンサルティング企業と提携して正確・迅速な情報把握
- 米国内の業界団体を通じた情報収集
- サプライチェーン上のボトルネックを特定し、発動後のシミュレーションを実施
- パブリックコメントや公聴会などを通じて積極的に提言
- 業界団体を通じた提言活動
- 不合理な点について積極的にロビイング活動を展開
- 関税コストの価格転嫁か利益圧縮かの判断
- 在庫活用などによる価格据え置きの検討
- 生鮮品など在庫として保有できない商品は価格転嫁を検討
- USJTA(米日貿易協定)を基盤として関税免除を継続的に要求
- 農産物関税の譲歩やエネルギー分野での協力を通じた交渉強化
中長期的対応策
1. 市場の多角化と地理的分散- 米国市場への過度な依存を避け、アジア(インドやインドネシアなど)、中東、アフリカなどの新興市場への現地生産拠点拡大
- 現地ニーズに即した車両提供、現地雇用創出
- ドイツや韓国などの主要輸出国と連携して多国間での対応策を模索
- EV(電気自動車)、自動運転技術、水素燃料電池車など次世代車両の研究開発を加速
- 自動運転やコネクテッドカーの開発も加速し、次世代モビリティ市場での競争力を向上
- 再生可能エネルギー、AI、バイオテクノロジーなどの成長産業への投資を強化
- 地域ごとの特色を活かした産業クラスターを形成
- 生産・調達・販売の地理的分散化を図り、サプライチェーンの柔軟性を向上
- 複数の生産拠点を維持しながら迅速に生産地を変更できる体制を構築
- 中国製部品を中国国内向けに、米国向け製品には中国製品を使わないようにするなど、サプライチェーンのデカップリング(分断)を推進
- 中国→メキシコ→米国というサプライチェーンの見直し
- トヨタ自動車、パナソニックエナジー、本田技研工業などが米国で大型投資を実施
- 製造業における米国での雇用創出数では、日本が16年連続で1位を維持
- トランプ政権の「米国内生産奨励」政策に対応
- 自動車産業での雇用減少に備え、職業訓練プログラムを拡充
- 中高年労働者にも対応したスキルアップ支援
- 新たな産業への移行を円滑化
- 地域経済への影響を最小限に抑える施策
日本政府の対応と課題
交渉戦略の現状
日本政府は、中国やEUが対抗措置を示唆する中で、報復措置を控えながら交渉を進める方針を示している。しかし、G7サミット中の日米首脳会談は30分と短く、関税に関する合意は「協議継続」のみにとどまった。石破首相は「双方の認識は一致していない」と述べており、交渉の難しさを物語っている。
政府は中小企業の価格転嫁を支援し、それを阻む取引を監視することがミッションとなっている。また、自民党の支持基盤である農家への影響も懸念されており、農産物関税の譲歩やエネルギー分野での協力を通じた交渉強化が検討されている。
参院選への影響
7月20日に投開票が有力視されている参院選の前後で交渉の結果が出ると、石破政権にとっても非常に重要となる。与党に不利な状況になれば日本の株式市場にも悪影響が増幅されると指摘されている。野村證券は、自動車関税が25%のまま据え置かれるシナリオを想定しており、この場合、日本株見通しにおける企業業績への影響は中立的と見ている。
まとめ – 不確実性の中での戦略的対応が鍵
トランプ政権の相互関税政策は、日本経済、特に自動車産業に長期的な影響を及ぼす可能性が高い。7月9日という期限が迫る中、赤沢大臣の交渉は難航しており、日米間の立場の隔たりは大きい。
企業にとっては、不確実性の高い経営環境の中で、特定国への過度な依存リスクを回避し、生産・調達・販売の地理的分散化を図ることが不可欠だ。政策の不確実性が高い中で、日本企業は正確・迅速な情報把握、自社サプライチェーンへの影響分析、そして損失最小化の方策立案のサイクルが重要となる。
日本は、二国間協定(USJTAなど)やWTOの枠組みを効果的に活用しつつ、米国側との協調関係を構築することが不可欠である。同時に、中長期的には、国内での技術革新の促進、供給体制の多国間化、新たな産業の育成を進めることで、経済全体の競争力を強化することが求められている。
トランプ政権の保護主義政策は、日本企業に対して多岐にわたる課題をもたらしているが、これを契機として産業構造の転換と国際競争力の強化を図ることが、日本経済の持続的成長につながる可能性もある。不確実性の時代だからこそ、柔軟かつ戦略的な対応が求められている。
関連記事
参照サイト: JETRO | みずほ銀行 | TRADE.JP | 野村総合研究所
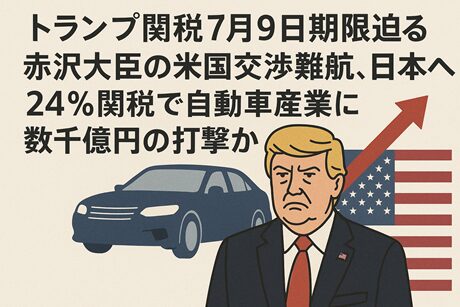
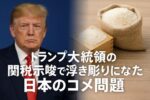



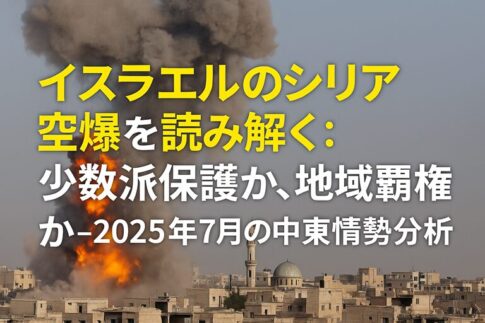


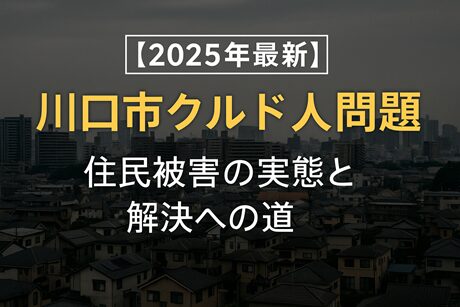

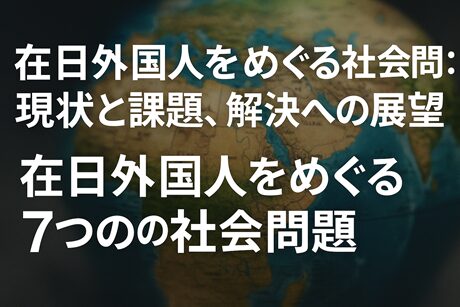

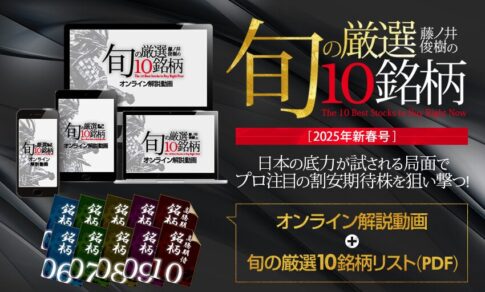





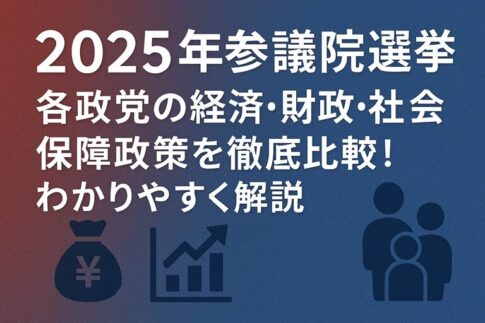


コメントを残す